相続した不動産を売却する流れと注意点|費用や税金特例まで徹底解説
2025.07.04

相続した不動産を売却する場合、相続登記や相続税の納付など適切な手続きを行ったうえで、売却活動を始める必要があります。場合によっては節税につながる特例が適用になる可能性もあるため、時期を考慮しながら早めに行うことが大切です。
相続した不動産を手際よく売却できるよう、不動産を売却する流れや遺産分割、かかる費用や特例のほか、注意点まで解説します。
目次
相続した不動産を売却する流れ

相続した不動産を売却する手順は、以下のとおりです。
- 1.遺言書の有無を確認する
- 2.相続登記をする
- 3.不動産を売却する
- 4.相続税を申告し納付する
- 5.確定申告を行う
1.遺言書の有無を確認する
被相続人が亡くなり、相続が発生した際、まずは遺言書の有無を確認します。遺言書が法的に有効であれば、内容に従って相続や遺産分割が必要です。
遺言書がない場合や、あっても日付や署名がないもの、内容が不明瞭な場合は、法定相続人で遺産分割協議を行わなければなりません。相続発生後3ヶ月以内に、遺産を相続するか放棄するかを決めましょう。
2.相続登記をする
相続した不動産を売却するには、不動産の名義を変更する相続登記を必ず行う必要があります。相続登記が完了していないと、売却契約において不動産の所有者が相続人であることを証明できず、売却を進められません。
また、2024年4月1日以降、相続登記は義務化されています。
名義変更や相続登記に必要な書類については、以下の記事をご確認ください。
3.不動産を売却する
相続登記後、売却を依頼する不動産会社を選定しましょう。仲介を依頼する場合は不動産会社と媒介契約を結び、買主が見つかったら物件を売却します。一方、買取を依頼する場合は、不動産会社と売買契約を結び、物件を引き渡します。
物件の売却については、以下の記事も参考にしてみてください。
4.相続税を申告し納付する
相続税は、相続開始から10ヶ月以内に申告と納付を行う必要があります。相続した不動産を売却した場合、売却額に応じた金額を収めます。
なお、申告期限までに売却が間に合わなかった場合でも、法定相続割合で仮申告が可能です。放置すると延滞税が発生するため注意しましょう。
5.確定申告を行う
相続した不動産を売却し、利益が生じた場合は、翌年の確定申告で譲渡所得税の申告・納付が必要です。譲渡所得税とは住民税と所得税のことで、物件の所有期間によって税率が異なります。
なお、譲渡所得税は一定の条件を満たせば特例が適用されることも。詳細は後述しています。
【不動産を相続】遺産分割はどうする?方法は4つ

遺産分割には、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4つの方法があります。
1.現物分割
現物分割とはいくつかの遺産(相続財産)をそのままの状態で引き継ぐ方法です。不動産や車などを現物のまま分けるため、相続手続きがシンプルな点がメリット。ただし、不動産の価値や法定相続割合に応じて公平に分配できないため、相続人間で不満が発生しやすいでしょう。
2.換価分割
換価分割は、不動産等を売却して得た現金を法定相続割合に応じて分配する方法です。公平に資産を分けられるのがメリットといえます。一方で、売却価格が安価になったり、諸経費が差し引かれたりすることから、手元に残る金額が予想より少なくなるリスクがあります。
3.代償分割
代償分割は、不動産等を多く相続した相続人が、他の相続人に代償金を支払うことで公平な分割を実現する方法です。特定の相続人が引き継ぐことで分配しやすい反面、経済的負担が重くなったり、支払い能力の問題で揉めたりする可能性があります。
4.共有分割
共有分割とは、遺産を法定相続割合で共有する分割方法です。相続した不動産等を複数の相続人が共同所有できるため、公平に分割できます。ただし、相続人全員の同意がないと自由に活用できず、管理処分が難しいため、避けるのが無難です。
不動産を相続して売却するまでにかかる費用

不動産を相続して売却するまでに、主に以下の費用が発生します。
| 費用 | 概要 |
|---|---|
| 登録免許税 | 相続登記の際にかかる税金 |
| 相続税 | 遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額に対しかかる税金 ※遺産総額が基礎控除額の範囲内であれば不要 |
| 譲渡所得税 | 不動産を売却後、利益が生じた場合に納める住民税と所得税 |
| 印紙税 | 相続した不動産を売却する際に発行する売買契約書に対しかかる税金 |
| 仲介手数料 | 不動産の売却にあたり、不動産会社に仲介を依頼した場合に発生する費用 |
| その他の費用 | ・戸籍謄本や不動産の登記事項証明書など、必要書類の取得費用 ・相続登記を司法書士に依頼した場合の司法書士報酬など |
【節税】相続した不動産の売却で適用される特例4つ

相続した不動産を売却する際、特例が適用される可能性があります。賢く利用して、節税につなげましょう。
1.相続税の取得費加算の特例
取得費加算の特例とは、譲渡所得税を計算する際に相続税額を取得費として加算できる特例です。適用することで、譲渡所得税を軽減できます。
利用するには、以下3つの要件を満たす必要があります。
- ・相続や遺贈により財産を取得した者であること
- ・その財産に相続税が課されていること
- ・相続税の申告期限の翌日以降、3年10ヶ月以内に譲渡していること
2. 相続空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却する場合、3,000万円の特別控除を受けられます。譲渡所得が3,000万円以下であれば、適用により税負担がゼロになる可能性も。
適用には以下の要件を満たす必要があります。
- ・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- ・区分所有建物登記がされていない建物であること
- ・相続の開始の直前に被相続人が一人で居住していた家屋であること
- ・売主が相続や遺贈によりその不動産を取得したこと
- ・相続開始から3年経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
- ・売却代金が1億円以下であること
- ・相続時から譲渡時まで事業用・貸付用・居住用に利用されていないこと
- ・一定の耐震基準に適合していること
- ・特別な関係者への譲渡でないこと(親子や夫婦など)
なお、前述した取得費加算の特例との併用はできません。
3.マイホーム売却の3,000万円特別控除
相続後に居住していた不動産を売却した場合、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けられます。前述の「相続空き家の3,000万円特別控除」との違いは、自分が日常的に住んでいたマイホームや敷地が対象になること。
住まなくなった日から3年が経過する年の12月31日までに売却しなければならないなど、いくつか適用要件があります。
4.小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、相続した宅地の評価額を最大8割減額できる特例です。適用されると、相続税が大幅に減額されます。対象となるのは土地のみで、居住用や事業用など種類によって適用要件が異なります。
相続した不動産を売却する際の注意点4つ
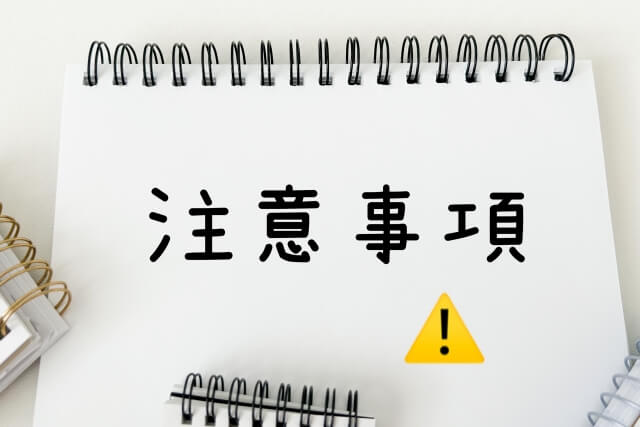
相続した不動産を売却する際、特例を利用するなら3年以内の売却を目指しましょう。不動産を共有名義にしている場合は、相続人全員の同意を得る必要があります。不動産の取得費と取得期間は引き継がれる点に留意し、単独登記型の場合は贈与にならないよう注意してください。
1.特例を利用したい場合は3年以内に売却する
相続した不動産の売却において特例を利用したい場合は、3年以内の売却を目安に進めましょう。前述した「取得費加算の特例」や「相続空き家の3,000万円特別控除」は、適用期限が相続開始から3年以内と決められています。期限を考慮して早めに準備することが重要です。
2.共有名義の不動産売却には全員の同意を得る
共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意を得なければなりません。同意を得られない場合、手続きが長引き不動産価格が下がるリスクがあります。
3.取得費と取得期間は引き継がれる
相続した不動産の取得費と所有期間は、親の購入時点の情報を引き継ぎます。譲渡所得は不動産の取得費や取得期間をもとに計算されるため、確認しておくことが必要です。
取得費は親が購入時に契約した売買契約書を見てみるとよいでしょう。見つからない場合は代替資料を探す必要があるため、早めの準備が肝心です。
4.単独登記型の場合は贈与にならないようにする
単独登記型で不動産を売却する場合、贈与とみなされないように注意が必要です。単独登記型は、換価分割の際に不動産を特定の相続人が単独所有し、売却後に現金(代償金)を他の相続人に分配する方法です。
適切な対策をしなかった場合、現金の分配が贈与とみなされるリスクも。遺産分割協議書に「換価分割を目的として不動産を取得する」という内容を明記し、リスクを回避しましょう。
相続した不動産を売却する流れを理解し、売却手続きに踏み切ろう

相続した不動産の売却では、遺言書の確認と相続登記を済ませ、売却後に相続税の申告・納付や確定申告が必要です。節税につながる特例が利用できることもあるため、売却を決めたら早めに手続きを開始しましょう。
相続不動産の売却にお悩みの方は、住栄都市サービスまでご相談ください。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。








