土地の相続税評価額とは?計算方法や減額要件までわかりやすく解説
2025.08.29

土地を相続したとき、まず確認すべきなのが相続税評価額です。この評価額は、相続税の金額だけではなく、遺産分割や将来の売却にも大きく関わってきます。
本記事では、相続税評価額の基本から具体的な計算方法、評価を下げられる条件、売却時の注意点までをわかりやすく解説します。損をしないために、まずは正しい知識を身につけましょう。
目次
土地の相続税評価額とは?知っておきたい基礎知識

土地を相続した際、まず把握すべきなのが相続税評価額です。これは、相続税をいくら納めるべきかの判断基準になる金額で、土地の現金換算の価値ともいえます。正確な納税のためにも、評価額の仕組みや必要書類をしっかり理解しておきましょう。
相続税評価額とは
相続税評価額とは、土地や建物などの財産を「税金の計算用に評価した金額」のことです。相続税を計算するための基準として、国が定める方法で算出されます。
同じ土地でも、場所や利用状況により評価額は大きく変わることがあるため、単に面積や地価を見ればよいというわけではありません。相続税を正しく計算するには、評価額の仕組みを理解するのが大事です。
評価額の計算に必要な資料と準備
相続税評価額を正しく計算するためには、以下の書類が必要です。計算方法によって必要な資料も変わるため、事前に確認しておきましょう。
| 書類名 | 目的・内容 | 備考・補足 |
|---|---|---|
| 固定資産税の課税明細書 | 土地の固定資産税評価額を確認するために使用 | 地方自治体から毎年送付 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 土地の所有者、地目、面積、持分割合などの詳細情報を確認 | 法務局で取得可能 |
| 路線価図(路線価方式用) | 道路ごとの1平方メートルあたりの単価を確認 | 国税庁が毎年公表 |
| 倍率表(倍率方式用) | 固定資産税評価額にかける倍率を確認 | 国税庁が毎年公表 |
相続税評価額の2つの計算方法|路線価方式と倍率方式

土地の相続税評価額は、路線価方式と倍率方式の2つの方法で算出します。どちらを使うかは土地の所在地などによって異なり、それぞれ必要な書類や確認手順も変わります。ここでは、その基本的な仕組みと、具体的な計算方法をわかりやすく解説します。
1.路線価方式|路線価が定められている地域
路線価方式とは、国税庁が毎年7月に発表する路線価の対象となる土地の面積をかけて、その土地の評価額を算出する方法です。
【計算方法】
1.路線価を確認する
路線価図で、接する道路の1平方メートルあたりの価格(千円単位)を調べる
2.土地の面積を確認する
登記事項証明書や固定資産税課税明細書で面積を確認
3.計算式に当てはめる
路線価×面積(平方メートル)
上記の式を用い評価額を計算する
奥行きが極端に短い・長い場合は補正率で調整したり、複数の道路に面していれば、影響加算率を使って加算したりする必要があるため、注意が必要です。
評価の誤りは税務署に指摘されるおそれがあるため、慎重に進めましょう。
2.倍率方式|路線価が定められていない地域
倍率方式は、路線価が定められていない土地の計算に用いる方法です。土地の固定資産税評価額に、地域ごとに決められた倍率をかけて評価額を出します。
【計算方法】
1.固定資産税評価額を確認する
納税通知書や課税明細書で土地の評価額をチェックする
2.倍率を調べる
国税庁の「倍率表」で、対象地の所在地・地目に合った倍率を確認する
国税庁|財産評価基準書路線価図・評価倍率表
3.持分割合がある場合は確認する
共有名義の土地なら、自分の持分割合を登記簿で確認
4.計算式に当てはめる
固定資産税評価額×倍率×持分割合(必要に応じて)
上記の式を用い評価額を計算する
なお、地目が登記と異なる場合は現況で評価します。たとえば、登記上農地となっていても、実際に宅地として使っていれば、宅地として評価されるため注意が必要です。
相続税評価額を減額できる土地|権利関係
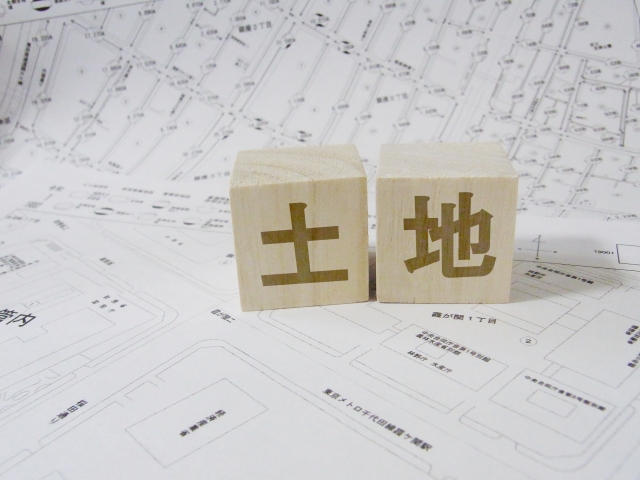
土地の利用に制限がある場合、相続税評価額が減額されることがあります。たとえば建物を貸していたり、土地を借りて使っていたりする場合が該当します。この章では、権利関係が評価額に与える影響と、具体的な計算方法を解説します。
建物を貸している土地|借家建付地
アパートや貸家の敷地として使われている貸家建付地は、自由に使えない制限があるため相続税評価額が減額されます。
【計算式】自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合)
借家権割合は全国一律30%です。
借りて使っている土地|借地権
借地権とは、地主から土地を借りて建物を所有する権利で、相続財産として評価されます。借地権は土地を所有していなくても、課税対象となるため注意が必要です。
【計算式】自用地評価額×借地権割合
借地権割合は路線価図で確認可能です。
相続税評価額を減額できる土地|土地の状態

相続税評価額は、以下のような土地の状態の場合、減額されます。
| 土地の状態 | 減額の理由・条件 | 評価方法の概要(簡易) |
|---|---|---|
| 500㎡以上の大規模地 | 規模が大きいほど分割売却が前提となり、単価が下がる傾向がある | 路線価×奥行価格補正率×不整形地等の各種画地補正率×規模格差補正率×土地の面積 |
| 不整形地 | 建物が建てにくく、市場価値が下がる | かげ地面積を除外し、不整形補正率をかけて算出 |
| 間口が狭い土地 | 車両の出入りや建築制限がある場合がある | 路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×土地の面積 |
| 奥行が長い土地 | 奥まった部分の利用価値が低いため | 路線価×奥行価格補正率×奥行長大補正率×土地の面積 |
| 線路・踏切に隣接 | 騒音や振動により居住性・資産価値が下がる | 通常の評価額から10%減額 |
| がけ地を含む土地 | 実質的に使用できない部分がある | 路線価×奥行価格補正率(がけ地含む)×不整形地等の各種画地補正率×がけ地補正率×土地の面積(がけ地含む) |
| セットバックが必要な土地 | 道路幅が4m未満で一部後退(セットバック)しなければならない | セットバック部分は評価額の70%相当額を控除 |
相続税評価額と実際の売却価格はどう違う?

土地の相続税評価額と、実際に売却したときの価格(時価)は一致しないことがほとんどです。評価額はあくまで「税金計算用の基準」であり、実際の市場価格とはズレがあります。ここでは、両者の違いや注意すべき点について整理します。
評価額は売却価格より低めに設定される
相続税評価額は、実際の売却価格とは異なります。これは、相続税評価額が納税者の負担を軽減し、不公平が生じないように配慮された制度だからです。
実際に不動産が売れる価格は「時価」と呼ばれ、路線価はその時価のおよそ8割に設定されています。相続時の評価額と実際の取引価格には差があるのが一般的です。
売却価格が評価額に影響を与えるケースもある
相続税における土地の評価は、通常は路線価を基に算出され、一定の条件を満たせば売却価格が評価額として認められることがあります。
【条件】
- 1.売却価格が相続税評価額を下回っている
- 2.売却先が利害関係のない他人である
- 3.売り急ぎなどで売却価格を著しく下げていない
- 4.相続から売却までの期間が長く空いていない
実際の市場価格に基づいて評価することで、より公平で合理的な課税が実現されます。
遺留分の基準は時価で考えられる場合がある
遺留分は相続開始時の時価評価にて計算します。
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることが保障されている相続財産の取り分のこと。相続税評価額を基準に遺留分を考えていると、後になって実際の時価で見直した際に遺留分を侵害していたことが判明し、争いとなるケースもあるため十分注意しましょう。
【土地の相続税評価】よくある質問

この章では、よく寄せられる質問をもとに、見落としがちなポイントや注意点をわかりやすく解説します。
親族へ時価より安い値段で売ったら贈与税はかかりますか?
時価より低い金額で売買すると贈与税の対象となり、追加徴税の恐れがあります。特に親族間での不動産売買では「家族だから安くしてあげよう」となりがちなため十分に注意が必要です。親族間でも適切な時価で取引しましょう。
私道の相続税評価はどうなりますか?
私道の評価は用途により異なります。
不特定多数が通行するような私道は評価されません。一方、特定の人だけが使う私道は、路線価方式や倍率方式で評価した価格の30%相当額で評価します。行き止まり道路などが対象で、通り抜け道路は評価の対象外です。
青空駐車場の相続評価はどうなりますか?
貸駐車場として利用している土地は、青空駐車場のように未舗装・簡易な設備のみの場合、相続税評価では「雑種地」として扱われます。小規模宅地等の特例が使えないため、評価額が高くなる傾向があります。
節税対策として、整備状況の見直しを検討するのも1つの手。条件によって小規模宅地等の特例が適用される駐車場もあるので注意が必要です。
自分の土地の相続税評価額を計算してみよう

土地を相続したら、まずは相続税評価額を正しく把握することが大切です。評価額は相続税の金額だけではなく、遺産分割や売却判断にも影響します。土地の形状や貸し借りの有無によっては減額されるケースも。
必要な書類をそろえれば、自分でおおまかな評価額を調べることも可能です。ただし、土地の評価は専門性が高いため、不安がある場合は税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。

