相続税の税率はどのくらい?計算方法や節税できる制度までわかりやすく解説
2025.08.08

相続が発生したときに気になるのが「相続税はいくらかかるのか?」という点ではないでしょうか。実は、相続税には「いくらまで無税か」を判断するための基礎控除があり、ケースによっては申告も納税も不要となることがあります。
本記事では、相続税がかかる基準から具体的な計算方法、さらに節税につながる控除や特例制度まで、わかりやすく解説します。
目次
相続税の税率はどう決まる?|仕組みと速算表の見方

相続税は、もらった財産の金額に応じて税率が変わる仕組みです。ただし、計算には速算表や相続人の関係性といったポイントも影響します。ここでは、相続税率の決まり方と、速算表の使い方をわかりやすく解説します。
相続税は「もらった金額」に応じて税率が変わる仕組み
相続税は、相続人が実際に「いくら相続したか」によって税率が決まります。遺産が多いほど税率も上がる累進課税の仕組みが採用されていて、10〜55%まで段階的に設定されています。
ただし、遺産総額に直接税率がかかるわけではなく、法定相続分で分けた金額に対して税率を適用する点がポイントです。
相続税の速算表を使えば、税率と控除額がわかる
相続税の計算では、速算表と呼ばれる税率一覧を使います。速算表は、法定相続分に応じた取得金額ごとに、適用される税率と控除額を確認できる表です。例えば、法定相続分で2,000万円を取得する場合は、税率15%、控除額50万円が適用されます。
【相続税速算表】
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続人の続柄によっては税金が2割アップするケースもある
相続人が被相続人の配偶者や子ども以外である場合、相続税が2割加算されるため注意が必要です。これは「相続税負担の公平性を保つため」という考えに基づいた制度。
相続の際には、対象となる相続人の関係性をしっかり確認することが、不要な負担を避ける第一歩となります。
相続税の税率はどうやって計算する?具体的な流れ

相続税の計算は、決まった手順に沿って進めればそれほど難しくありません。ここでは、遺産の総額を出すところから、実際の納税額を求めるまでの流れを5つのステップでわかりやすく解説します。
ステップ1|まずは遺産の合計金額を出す
相続税の計算は、亡くなった方のすべての財産を合計することから始まります。例えば、不動産、預貯金、株式、生命保険、退職金などが対象です。一方で、借金や未払費用、葬儀代などはマイナス項目として差し引けます。
【課税対象となる財産】
| 項目 | 課税対象の内容 | 非課税枠 |
|---|---|---|
| 本来の相続財産 | 現金、預貯金、株式、有価証券、土地、建物、貸付金、特許権、著作権など | – |
| みなし相続財産 | 生命保険金、死亡退職金など | 500万円×法定相続人の数まで |
| 相続時精算課税財産 | 相続時精算課税制度を適用した財産 | 累計贈与額2,500万円まで |
| 生前贈与財産 | 相続開始前7年以内の贈与財産 | 3年超7年以内総額100万円まで |
| 相続時精算課税財産 | 相続時精算課税制度を使って生前に贈与された財産(贈与税の申告済) | 累計贈与額のうち2,500万円まで |
【課税対象から引かれる財産・費用】
| 相続財産から引かれる項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 債務 | 借入金、未払金、未払税金など |
| 葬式費用 | 葬儀費用、通夜費用、埋葬料など |
| 香典 | 遺族に渡されるため相続財産にはならない |
ステップ2|基礎控除を引いて課税対象額を計算
合計した遺産の金額から、以下の式で算出される基礎控除額を差し引きます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、配偶者と子ども1人の2人が相続人の場合
3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
つまり、遺産総額が4,200万円以下なら、相続税はかかりません。
ステップ3|法定相続分で分けて1人あたりの金額を出す
課税対象となる遺産を、民法上の法定相続分で分けたと仮定し、課税される遺産総額を各法定相続人の法定相続分に基づき計算します。
課税遺産総額×法定相続分=各相続人の取得金額
ステップ4|速算表で税率と控除額をあてはめて計算
ステップ3で出した1人あたりの金額に、速算表の税率と控除額をあてはめて仮の税額を算出しましょう。これを相続人それぞれに対して行い、全員分を合計したものが相続税の総額となります。
ステップ5|実際の取得割合で再按分する
相続税の総額が出たら、実際の遺産の分け方に応じて税額を再計算します。
さらに、配偶者の税額軽減や未成年控除、障害者控除などの特例を適用すれば、最終的な納税額が決定。特例の詳細については後述します。
相続税の負担を軽減!知っておきたい4つの制度

相続税には、特定の条件を満たす場合に、税負担を軽減できる特例や控除制度があります。ここでは、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除の4つの主な制度について解説します。
1.小規模宅地等の特例
相続財産のうち、被相続人や同居親族が使用していた居住用・事業用・貸付用の土地について、一定の条件を満たす場合、相続税評価額を最大80%まで減額できる特例です。居住用宅地は330㎡まで80%、事業用宅地は400㎡まで80%、貸付用宅地は200㎡まで50%の減額が適用されます。
小規模宅地等の特例について詳しく知りたい人は以下をチェックしてください。
2.配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が相続する財産について、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税が非課税となる制度です。配偶者の生活保障を目的として相続税の負担が軽減されます。
3.未成年者控除
相続人が18歳未満の場合「相続開始から18歳に達するまでの年数×10万円」が相続税額から控除される制度です。教育費や養育費の負担を考慮し、未成年者の生活を支援する目的で設けられています。
4.障害者控除
相続人が85歳未満の障害者である場合「相続開始から85歳に達するまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)」が相続税額から控除されます。控除しきれない場合は扶養義務者の相続税から控除が可能です。障害者控除は、障害者の長期的な生活保障の両立を図る制度として重要な役割を果たしています。
相続税の節税方法を詳しく知りたい人は以下をチェックしてください。
相続税の税率の計算例

計算方法に基づいた実際の計算例です。
【亡くなった被相続人の財産7,000万円を配偶者が5,000万円、子2人が1,000万円ずつ相続した場合】
①相続財産総額7,000万円
②課税遺産総額を計算
- 1.基礎控除:3,000万円+600万円×3(法定相続人数)=4,800万円
- 2.課税遺産総額:7,000万円-4,800万円=2,200万円
③課税遺産総額を相続人で分配する
法定相続分=配偶者:1/2、子供2人:1/4ずつ
配偶者:2,200万円×1/2=1,100万円
子供A:2,200万円×1/4=550万円
子供B:2,200万円×1/4=550万円
④相続税額を計算する
【速算表(税率15%、控除額50万円)を適用】
配偶者:1,100万円×15%-50万円=115万円
子供A:550万円×15%-50万円=32.5万円
子供B:550万円×15%-50万円=32.5万円
相続税の総額:115万円+32.5万円+32.5万円=180万円
⑤各相続人が納付すべき相続税額の計算
1.実際の相続割合で按分する
【相続遺産額】
配偶者:5,000万円/7,000万円=0.71
子供A:1,000万円/7,000万円=0.14
子供B:1,000万円/7,000万円=0.14
※按分割合は、相続人の合意があれば、小数点2位以下で調整可能
【相続税額】
配偶者:180万円×0.71=127.8万円
子供A:180万円×0.14=25.2万円
子供B:180万円×0.14=25.2万円
2.配偶者の税額軽減
配偶者が相続する金額が1億6,000万円以内であるため、相続税は0円
結果:配偶者は無税、子供A・Bは25.7万円の納税が必要
相続税の申告・納税は10か月以内に行うのが必須
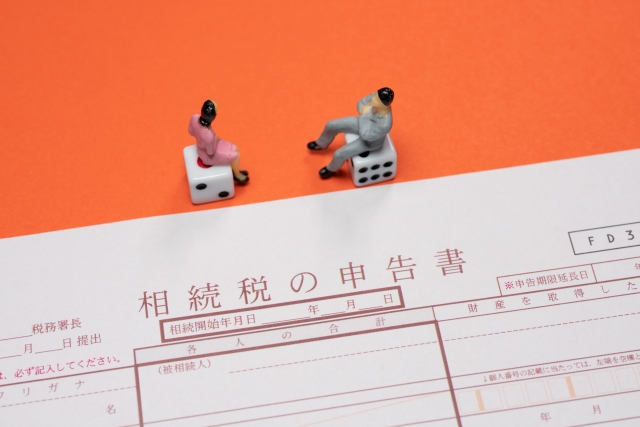
相続税の申告・納税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行いましょう。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。また、計算の結果課税がない場合でも、申告書の提出は必要なため注意が必要です。
例えば、1月10日に亡くなった場合、翌日の1月11日から起算して10ヶ月後の11月11日が申告期限となります。期限内の確認と適切な手続きが重要です。
自分のケースで相続税の税率を計算してみよう

相続税の計算においては、課税対象財産の把握や基礎控除額の計算が欠かせません。相続税率は取得金額や法定相続分に基づき決定され、特例や控除の適用により大きく変わる場合もあります。
自身のケースに当てはめて相続税の計算を行い、適切な申告・納税計画を立ててみましょう。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。







