遺産分割協議書の書き方|ひな形や例文・ポイントをわかりやすく解説
2025.07.15
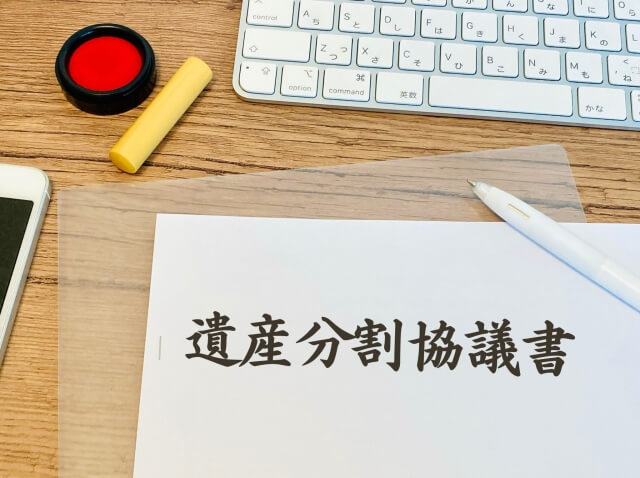
遺産分割協議書とは、相続人で遺産の分け方について話し合った内容をまとめた書類のことです。様式に法的な決まりはなく、自分で作成できます。とはいえ、書き方がわからず不安に感じる方もいるかもしれません。
本記事では遺産分割協議書の書き方を、ひな形や例文、ポイントとあわせて解説します。
目次
遺産分割協議書とは
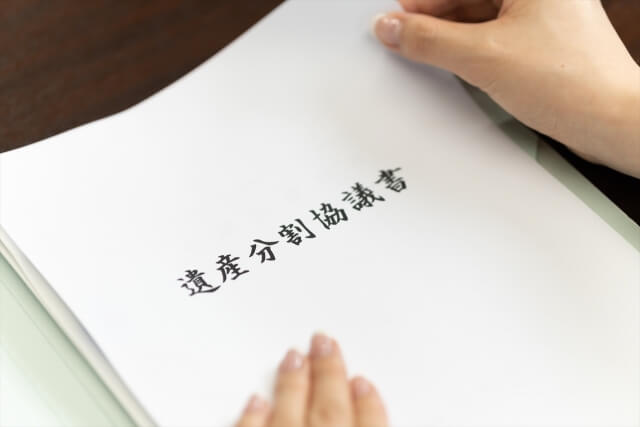
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割について話し合った内容をまとめた書類のこと。自分でも作成でき、相続税の申告期限までに作成しておくのが理想です。ここでは、遺産分割協議書の基本的な内容について解説します。
遺産分割について合意した内容をまとめた書類
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合い、合意した内容をまとめた書類のことです。法律で作成が義務付けられているわけではありませんが、相続人間のトラブルを防ぎ、相続手続きをスムーズに進めるために作成するのが一般的です。
自分でも作成できる?
遺産分割協議書の様式に法的な決まりはなく、自分でも作成できます。ただし書き方を間違えたり内容に不備があったりすると無効となり、適切に相続手続きが行えない場合があるため、注意が必要です。不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
いつまでに作成すればいい?
遺産分割協議書に作成期限はありません。ただし相続税の申告・納税は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。遺産分割協議が終わっていなければ、相続税の申告・納税はできないため、申告期限までには作成しておきましょう。
用紙はどこでもらえる?
遺産分割協議書の用紙は、自分で用意する必要があります。役所の窓口や法務局のサイトからダウンロードで取得できるわけではありません。
また様式はないため、必要な項目を押さえていれば手書き・パソコンなどで自由に作成してかまいません。用紙のサイズや色の指定もありませんが、A4の白い用紙が無難です。
【基本】遺産分割協議書のひな形と必ず入れる項目

ここでは、遺産分割協議書のひな形と、必ず入れる項目の内容について詳しく確認していきましょう。
【遺産分割協議書のひな形】
| 遺産分割協議書
被相続人 住栄太郎(生年月日) 被相続人住栄太郎の遺産相続につき、被相続人の妻住栄雅子、被相続人の長男住栄一郎、 1.住栄雅子は、次の遺産を取得する 本協議書に記載のない財産および後日判明した財産については、相続人住栄雅子が 以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証明するため、 令和〜年〜月〜日 |
前文
被相続人の情報の下に、下記のような前文を入れます。このとき、法定相続人全員の名前を挙げる必要があります。
(例)
| 被相続人住栄太郎の遺産相続につき、被相続人の妻住栄雅子、被相続人の長男住栄一郎、 被相続人の長女住栄花子の相続人全員が遺産分割協議を行い、次のとおりに遺産分割の 協議が成立した。 |
取得財産の内容
前文の下に、遺産分割協議で決まった取得財産の内容をそれぞれ記載します。なお、遺産内容の詳しい書き方は後述しているので、そちらを参考にしてください。
(例)
| 1.住栄雅子は、次の遺産を取得する (遺産の内容) 2.住栄一郎は、次の遺産を取得する (遺産の内容) 3.住栄花子は、次の遺産を取得する (遺産の内容) 4.本協議書に記載のない財産および後日判明した財産については、相続人住栄雅子が相続し、取得する。※ |
※の文章は、あとで財産や債務が判明した場合に備えて記載しておきましょう。
後文
遺産の取得内容を記載後、以下のような後文をつけます。
| 本協議書に記載のない財産および後日判明した財産については、相続人住栄雅子が相続し、 取得する。 ※以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証明するため、 本協議書を作成し、相続人全員が署名捺印のうえ1通ずつ所持する。 |
※の文章は、あとで財産や債務が判明した場合に備えて記載しておきましょう。
作成日付・相続人全員の情報
最後に作成日付と相続人全員の住所と氏名を書き、実印を押印します。
| 令和〜年〜月〜日 住所 〜〜〜 相続人 住栄雅子 印 住所 〜〜 相続人 住栄一郎 印 住所 〜〜 相続人 住栄花子 印 |
遺産分割協議書の書き方|遺産内容別の項目

遺産分割協議書に書く内容は、取得した遺産によって異なります。ここでは、遺産の内容別の書き方をみていきましょう。なお、生命保険金や死亡退職金は遺産分割の対象にはならないため、遺産分割協議書に書く必要はありません。
(1)不動産
記載内容:
(土地の場合)所在・地番・地目・地積
(建物の場合)所在・家屋番号・種類・構造・床面積
※マンションの場合はさらに詳しい内容が必要
※必ず登記簿謄本どおりに記載する
(2)預貯金
記載内容:銀行名・支店名・預貯金の種類・口座番号・名義人の氏名
(3)有価証券(株式)
記載内容:証券会社名・支店名・口座番号・発行会社名・保有株数
(4)自動車
記載内容:自動車登録番号・車体番号
※車検証を参照して以下のように記載
(例)
| 自動車登録番号 品川 987 あ 654 車体番号A123B−9876543 |
(5)債務
記載内容:契約内容・債務残高・債権会社名
(例)
| 金銭消費賃貸借契約 金 500,000円 債権者 〜〜株式会社 |
(6)配偶者居住権
配偶者居住権とは、被相続人が所有していた建物に居住する配偶者が、一定期間または死亡するまで住み続けられる権利のこと
(例)
| 被相続人住栄太郎の妻住栄雅子は、下記の建物の配偶者居住権を取得する。 存続期間は遺産分割協議書の成立日から住栄雅子の死亡日までとする。(以下、(1)同様に建物の詳細) |
遺産分割協議書|作成のポイント2つ

遺産分割協議書を作成する際は、相続人全員の実名での署名押印が必要です。また複数ページにわたる場合は、契印を押すようにしましょう。
1.相続人全員が実印で署名押印する
遺産分割協議書には必ず相続人全員の署名を行い、「実印」で押印します。名前がない相続人がいると、書類が無効となってしまうため注意しましょう。
また遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、全員が1通ずつ保管します。このとき、各書類が同じ内容であることを証明するため、すべての遺産分割協議書にかかるように割印も押しておきましょう。
2.複数ページの場合は契印を押す
遺産分割協議書が複数ページにわたる場合は、ページの間に相続人全員の契印を押します。契印とは、書類が2枚以上ある場合にそのつながりが真正であることを示す印のこと。
なお、遺産分割協議書を袋とじにして表紙に捺印すれば、契印は不要です。
遺産分割協議書をなくしてしまった場合は?

遺産分割協議書をなくしてしまった場合、他の相続人から原本を借りて相続手続きをする方法があります。原本を再度作成することも可能ですが、その場合は相続人全員の署名と押印が必要です。
他の相続人から協力を得られない場合、再作成はできません。遺産分割協議書は紛失しないよう、鍵のついた金庫や引き出しなどに保管しておきましょう。
遺産分割協議書の作成が難しい場合は誰に頼めばいい?

遺産分割協議書を自分で作成するのが難しい場合は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士に作成を依頼できます。専門家によって対応可能な相続手続きの範囲は異なるため、何を依頼したいかによって適切に選びましょう。
- ・遺産分割協議書の作成だけを依頼したい…行政書士
- ・遺産分割協議書の作成+相続人間のトラブルを解決したい…弁護士
- ・遺産分割協議書の作成+相続登記を依頼したい…司法書士
- ・遺産分割協議書の作成+相続税の手続きを依頼したい…税理士
遺産分割協議書は自分で作成できる!正しい書き方を知っておこう

遺産の分割方法について相続人全員で協議した内容をまとめたものが、遺産分割協議書です。様式に法的な決まりはなく、必要な項目を押さえていれば自分で作成できます。
なお、作成が難しい場合は専門家に依頼するのも一つ。まずはひな形を確認し、正しい書き方を知っておきましょう。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。





