遺産相続の相談はどこがいい?無料の相談先一覧や注意点を解説
2025.07.25

遺産相続に関する相談窓口は複数あり、内容によって適切な窓口が異なります。
本記事では、相続の相談は「どこにするべき?」「誰にすればいいの?」と迷う方へ、無料の相談先一覧や相談の流れ、注意点を解説。まずは話を聞いてから手続きを進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
相続の相談先一覧|無料で相談できる?
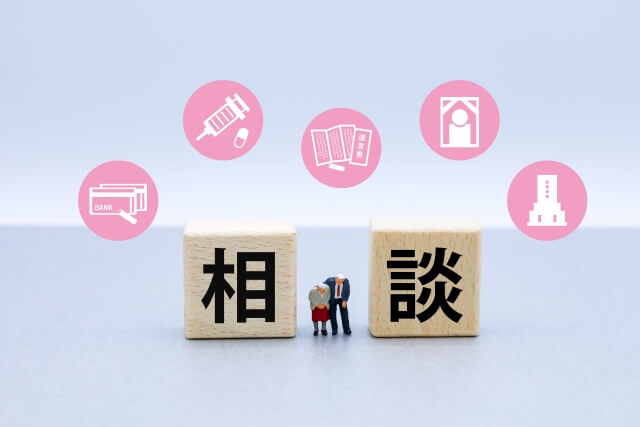
相続の相談は無料でできます。相談先は相談内容によって異なるため、悩みに応じた適切な窓口を選ぶことが大切です。以下の表を参考に、自分に合った相談先を探してみましょう。
| 相談先 | 相談内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 区役所・市役所 | 相続に関する基本情報 | 無料 |
| 国税局・税務署 | 相続税に関する基本情報 | 無料 |
| 銀行 | 預金の取り扱いや運用について | 相談のみなら無料 |
| 法テラス | 相続全般に関する情報 | 条件に該当すれば無料 |
| 弁護士 | 相続人間のトラブル | 初回相談無料の場合あり |
| 司法書士 | 相続登記 | 初回相談無料の場合あり |
| 税理士 | 相続税申告 | 初回相談無料の場合あり |
| 行政書士 | 書類作成の依頼 | 初回相談無料の場合あり |
区役所・市役所
区役所や市役所などの自治体では、相続の基本情報について相談できます。「何から手続きを始めたらいいかわからない」「どこに相談したらいいかわからない」といった悩みを抱えている方に向いています。無料で相談でき、誰でも気軽に利用できるのがメリット。
ただし、個別の具体的な相談や手続きの依頼はできません。自治体によっては弁護士や司法書士による無料相談会を実施している場合もあるため、ホームページを確認してみましょう。
国税局・税務署
国税局や税務署では、税の計算方法や書類の作成方法など、相続税に関する基本的な情報について相談できます。自治体同様、無料で相談が可能で、専用ダイヤルによる電話相談にも対応しています。
ただし、個別の具体的な相談は難しいのが実情。詳しい相談をしたい方や手続きを専門家に依頼したい方は、後述する税理士への相談がおすすめです。
銀行
被相続人の預金の取り扱いや運用で相談があるときは、銀行の窓口を利用しましょう。例えば名義人が亡くなると、その銀行口座は凍結され、預金を引き出すには凍結解除の手続きが必要です。銀行ではこうした口座手続きだけでなく、預金の運用方法についても無料で相談できます。
ただし相続人同士で意見がまとまっていない場合は、弁護士など専門家のサポートが必要になることも。また遺言信託などのサービスを使うと、別途費用がかかります。
法テラス
法テラスは、適切な相談窓口を知りたい場合や無料法律相談を受けたい場合などに利用できます。相談後、実際に弁護士や司法書士に手続きを依頼したい場合、手続きの費用を立て替えてくれる制度もあります。
ただし無料相談や費用の立て替えは、経済的に困難な方が対象で、一定の条件を満たす必要があります。条件に該当するかどうか、事前に法テラスのホームページで確認しておくとよいでしょう。
弁護士
相続人間のトラブルを解決したい場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士は代理人として交渉できる、紛争解決のプロ。相続放棄の相談や手続きの代行、相続人・相続財産調査、交渉内容をまとめた遺産分割協議書の作成なども依頼できます。
依頼内容に応じて報酬が必要ですが、初回相談は無料の事務所が多いため、相続トラブルを抱えている場合は頼ってみましょう。
司法書士
相続登記の悩みがある場合は、司法書士がおすすめです。相続登記とは相続で取得した不動産の名義変更手続きのことで、司法書士の専門分野。相談に応じてくれるだけでなく、手続きの代行も可能です。
初回相談は無料の事務所が多いため、まずは気軽に相談してみましょう。ただし弁護士のように相続人の代理人として交渉はできないため、すでにトラブルに発展している場合は弁護士への相談を推奨します。
税理士
相続税の悩みは、税の専門家である税理士への相談一択です。相続税の課税対象であるかの調査や申告代行、節税対策の相談にも乗ってもらえます。
初回相談は無料の事務所が多いですが、相続税申告の代行を依頼する場合は、遺産総額の0.5〜1%を相場とした報酬が必要となります。
行政書士
相続人・相続財産調査や戸籍謄本などの必要書類の収集、遺産分割協議書の作成など、相続手続きにおける書類業務のみを依頼したい場合は、行政書士に相談するとよいでしょう。
弁護士や司法書士と比較すると対応可能な範囲は限られていますが、最低限のサポートを受けたい場合におすすめです。初回相談は無料の事務所が多いですが、実際に手続きを依頼した場合の費用は事務所によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
相続の無料相談の流れ

相続の相談をするには、まず相談窓口を探すところから始めます。どのような流れで相談できるのか、ここでは市役所での無料相談の流れを見てみましょう。
(1)相続の無料相談窓口を設けている自治体を探す
自治体のホームページを確認したり、実際に問い合わせたりして、相談窓口の有無を確認する。
(2)電話やメールで予約する
予約方法は自治体によって異なるが、電話やメールなど指定の方法で希望日時に予約を入れる。
(3)相談の準備をする
相談時間は限られているため、相続関連の資料を用意したり、相談内容をまとめたりして聞きたいことをスムーズに聞けるように準備しておく。資料は相手用と自分用に2部あるとわかりやすい。
(4)無料相談に行く
相談した内容をメモできるように、筆記用具やノートを持参するとよい。
相続の相談をする際の注意点3つ
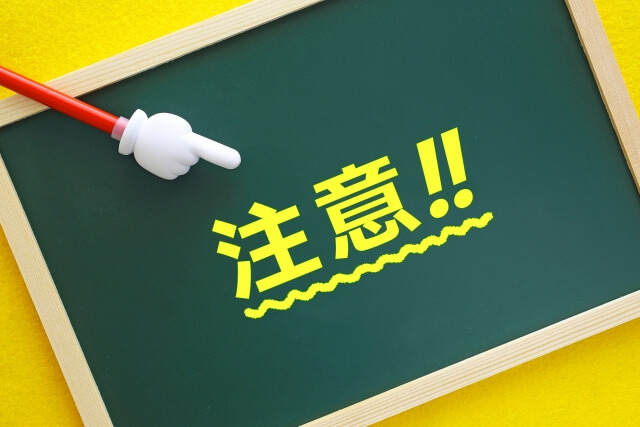
相続の相談をする際は、事務所の得意分野を見極めて自分に合った相談先を探すことが大切です。また事前に相談内容をまとめたり、参考資料を持参したりするとよいでしょう。
1.事務所の得意分野を見極める
事務所によって専門家の得意・不得意分野が異なるため、相続を得意とする事務所を選ぶことが大切です。例えば、同じ弁護士でも相続を得意とする弁護士と、離婚を得意とする弁護士がいます。
事前に事務所のホームページをチェックして、過去の実績や対応可能な案件を確認しておきましょう。
2.事前に相談内容をまとめておく
相談時間には限りがあるため、事前に相談したい内容をまとめておくと焦ったり聞き漏れが発生したりするのを防げます。多くの事務所で、初回相談は1回30分〜60分程度とされていることがほとんど。知りたい内容を漏れなく確認できるよう、メモなどにまとめておきましょう。
3.相談時に参考資料を持参する
相談時には、参考となる資料を用意し持参するのもおすすめ。例えば、相続人関係や遺産相続の内容を把握できる書類や遺言書などがあると、より具体的なアドバイスがもらえます。
手ぶらで行っても問題ありませんが、一般的な内容の説明にとどまってしまうことも。先述のとおり相談時間は限られているので、資料があるとスムーズに相談できます。
相続について一人で悩まず、まずは無料相談を活用してみよう

相続の相談をする際は、自分の悩みに合った適切な窓口を選ぶことが大切です。相談時には聞きたい内容をまとめたり、資料を持参すると具体的なアドバイスをもらいやすくなります。一人で悩まず、まずは無料相談に足を運んでみましょう。
不動産に関する相続手続きにお悩みの方は、ぜひ住栄都市サービスまでご相談くださいね。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。

