口座が凍結される理由・タイミングとは?事前に引き出すリスク・解除方法
2025.07.11

口座名義人が亡くなると、その事実が金融機関に伝わった時点で口座は凍結され、預金の引き出しや振込などすべての取引ができなくなります。急な支払いに困ることも多く、相続前の引き出しには注意が必要です。
本記事では、口座凍結の理由やタイミング、相続時のリスク、解除方法までを解説します。
目次
口座の凍結とは

銀行口座は、名義人の死亡など特定の条件を満たすと凍結され、預金の引き出しや振込といった取引がすべてできなくなります。急な支払いに対応できず、家族が困るケースも少なくありません。ここでは、口座凍結の意味や影響について解説します。
銀行口座のすべての取引が停止すること
口座凍結とは、銀行口座の入出金や振込、口座振替など、あらゆる金融取引が停止される状態を指します。たとえ口座に残高があっても、お金を引き出すことはできず、クレジットカードの引き落としや公共料金の支払いも止まってしまいます。
口座が解約されるわけではありませんが、再度利用するには金融機関での凍結解除手続きが必要です。
口座が凍結されるとどうなる?
凍結された口座はすべての取引ができなくなるため、生活に直結する支払いにも影響が出ます。家賃や光熱費の引き落としが止まり、延滞やサービス停止のリスクが生じることも。給与振込や生活費の出金もできず、突然の資金難に陥るケースもあります。
また、相続の場面では家族が預金の把握や管理に苦労することも多く、凍結された口座は放置しても自動で解除されないため、必ず所定の手続きが必要です。
口座が凍結されるタイミングと理由

口座が凍結されるのは、突然起きることではありません。金融機関が特定の事実を確認したタイミングで、預金の保護や不正防止を目的に凍結処理が行われます。ここでは、主な4つのケースについて具体的に解説します。
1.金融機関が名義人の死亡を確認したとき
名義人が亡くなったことを金融機関が確認すると、ただちに口座が凍結されます。多くは家族からの連絡によって判明しますが、新聞の訃報欄や公的機関からの情報で知るケースもあり、銀行から遺族へ確認の連絡が入ることも。
凍結の目的は、相続人や相続人以外の者による不正な出金を防ぐことにあり、以降の入出金や振込などすべての取引が停止されます。
2.債務整理の対象になったとき
債務整理を進めると、借入先の金融機関に通知が届いた時点で口座が凍結されることがあります。特に、その借入先の銀行に預金口座がある場合、残高を返済に充てる目的で凍結されるケースも。
一般的には、弁護士が債務整理の手続きを受任し、金融機関へ通知を送付した段階で凍結処理が開始されます。
3.不正利用の疑いがあるとき
口座が詐欺やマネーロンダリングなどの不正取引に使われた疑いがある場合、警察からの情報提供により金融機関が口座を凍結します。
名義人に心当たりがなくても、本人確認書類が盗まれて偽口座が作られていた場合、同一名義の関係のない口座まで凍結対象になることがあるため注意が必要です。
4.名義人が認知症と判断されたとき
名義人に認知症の兆候が見られた場合、金融機関は資産保護の観点から口座を凍結することがあります。親族からの申告や、窓口でのやり取り中に判断能力の低下が明らかになった場合がきっかけ。
これは、本人の財産を詐欺や不正出金から守るための措置であり、名義人の保護を最優先とした対応です。
相続で口座の凍結前に引き出すリスクと凍結後の対処法

名義人が亡くなると、その口座は金融機関により凍結され、預金の出し入れができなくなります。必要な資金を確保したいと考える家族も多いですが、口座凍結前に預金を引き出すことには注意が必要です。
ここでは、凍結前に引き出すことのリスクと、凍結後の正しい対応方法を解説します。
凍結前に引き出すと相続トラブルや放棄の制限につながることもある
名義人が亡くなった直後であっても、口座凍結前にお金を引き出すことは可能です。しかし、それを軽率に行うと、他の相続人との間で「不公平な取得」としてトラブルに発展する可能性があります。
また、引き出したお金を自身のために使った場合、相続を承認したとみなされ、後から相続放棄ができなくなるリスクもあります。たとえ葬儀費用であっても、遺産を使ったと見なされる可能性があるため、対応は慎重に行うべきです。
凍結後は仮払い制度が利用できる
預金口座が凍結された後でも、「預貯金の仮払い制度」を利用すれば、一定の条件のもとで預金の一部を引き出すことが可能です。この制度は2019年の法改正で導入され、相続人1名からの申請でも利用できます。
引き出せる上限は、1つの金融機関につき150万円までで、「預金残高×1/3×仮払い請求をする相続人の法定相続分」で算出されます。申請には戸籍謄本や印鑑証明などが必要で、引き出した金額は遺産分割時に精算対象となるため、使途を明確に記録しておくことが大切です。
相続で口座の凍結を解除する方法

名義人が死亡して口座が凍結された場合、その解除には相続手続きの完了が必要です。相続人は金融機関に所定の書類を提出し、遺産分割の内容や遺言書に基づいて正当な相続が確認されることで、口座の凍結が解除され、預金の引き出しなどが可能になります。
相続で口座の凍結を解除するために必要な書類
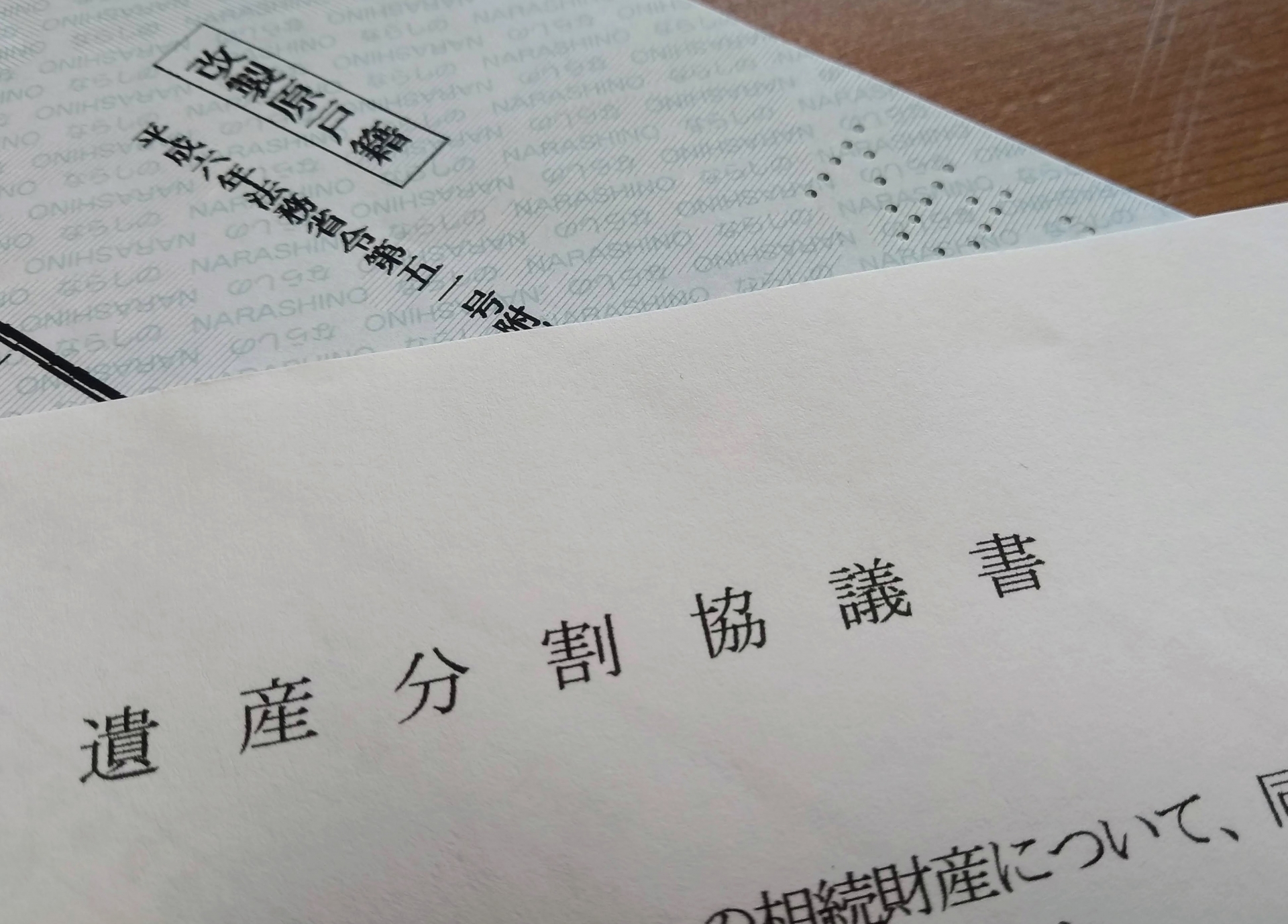
口座の凍結を解除するには、相続方法や遺言書の有無に応じて、必要な書類をそろえて提出する必要があります。一般的には、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書などが求められます。
事前に金融機関の案内を確認し、指示に従って正確に手続きを進めることが大切です。
| 状況 | 必要書類 | 補足事項 |
|---|---|---|
| 遺言書・遺産分割協議書がない共同相続 | 戸籍謄本 印鑑証明書 通帳・キャッシュカードなど |
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、法定相続人を確認できるすべての戸籍(相続情報一覧図で代替可) 法定相続人全員分 貸金庫の鍵がある場合も含めて準備 |
| 遺言書なし・遺産分割協議書あり | 遺産分割協議書 戸籍謄本 印鑑証明書 通帳・キャッシュカードなど |
原本で、資産の分割内容が明記されていること 出生から死亡までの連続した戸籍(相続情報一覧図で代替可) 法定相続人全員分 貸金庫の鍵がある場合も含めて準備 |
| 遺言書あり・遺言執行者なし | 遺言書 検認済証明書 戸籍謄本 印鑑証明書 通帳・キャッシュカードなど |
原本の提出が必要 家庭裁判所の発行、公正証書や保管制度利用時は不要 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、法定相続人を確認できるすべての戸籍(相続情報一覧図で代替可) 資産を受け取る相続人分 貸金庫の鍵がある場合も含めて準備 |
| 遺言書あり・遺言執行者あり | 遺言書 検認済証明書 戸籍謄本 印鑑証明書 通帳・キャッシュカードなど |
原本を用意 家庭裁判所の発行、公正証書や保管制度利用時は不要 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、法定相続人を確認できるすべての戸籍(相続情報一覧図で代替可) 資産を受け取る相続人分 貸金庫の鍵がある場合も含めて準備 |
相続で口座凍結する前にやっておきたい3つの対策

口座名義人が亡くなると、銀行口座は凍結され、預金の引き出しや振込ができなくなります。スムーズに相続手続きを進めるためには、亡くなる前の事前の準備が欠かせません。特に、家族の負担を減らすためには、次の3つの対策を行っておくことが効果的です。
【口座凍結前にしておくべきこと】
- 1.取引口座のリスト化:銀行名・支店・口座番号・預金種類・残高などを一覧で整理
- 2.通帳・印鑑の保管場所を家族と共有:手続き時に必要な物の所在を伝えておくとスムーズ
- 3.不要な口座は整理・解約:使っていない口座も凍結対象になるため、早めの整理が有効
これらの対策をあらかじめ講じておくことで、口座凍結後にも慌てずに対応でき、相続手続きの停滞やトラブルを未然に防ぐことができます。
口座の凍結は放置せず、慎重に対処しよう

口座が凍結されると、預金の引き出しや振込などの取引がすべてできなくなり、生活や相続手続きに大きな支障をきたします。
凍結は放置しても自動的に解除されず、手続きして解除されるまでに日数がかかるので、早めの手続きと事前準備が重要です。正しい知識を持って、慎重に対応しましょう。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。





