親の遺産を複数の子(兄弟姉妹)が相続する場合のルールとトラブルを防ぐポイント
2025.06.17
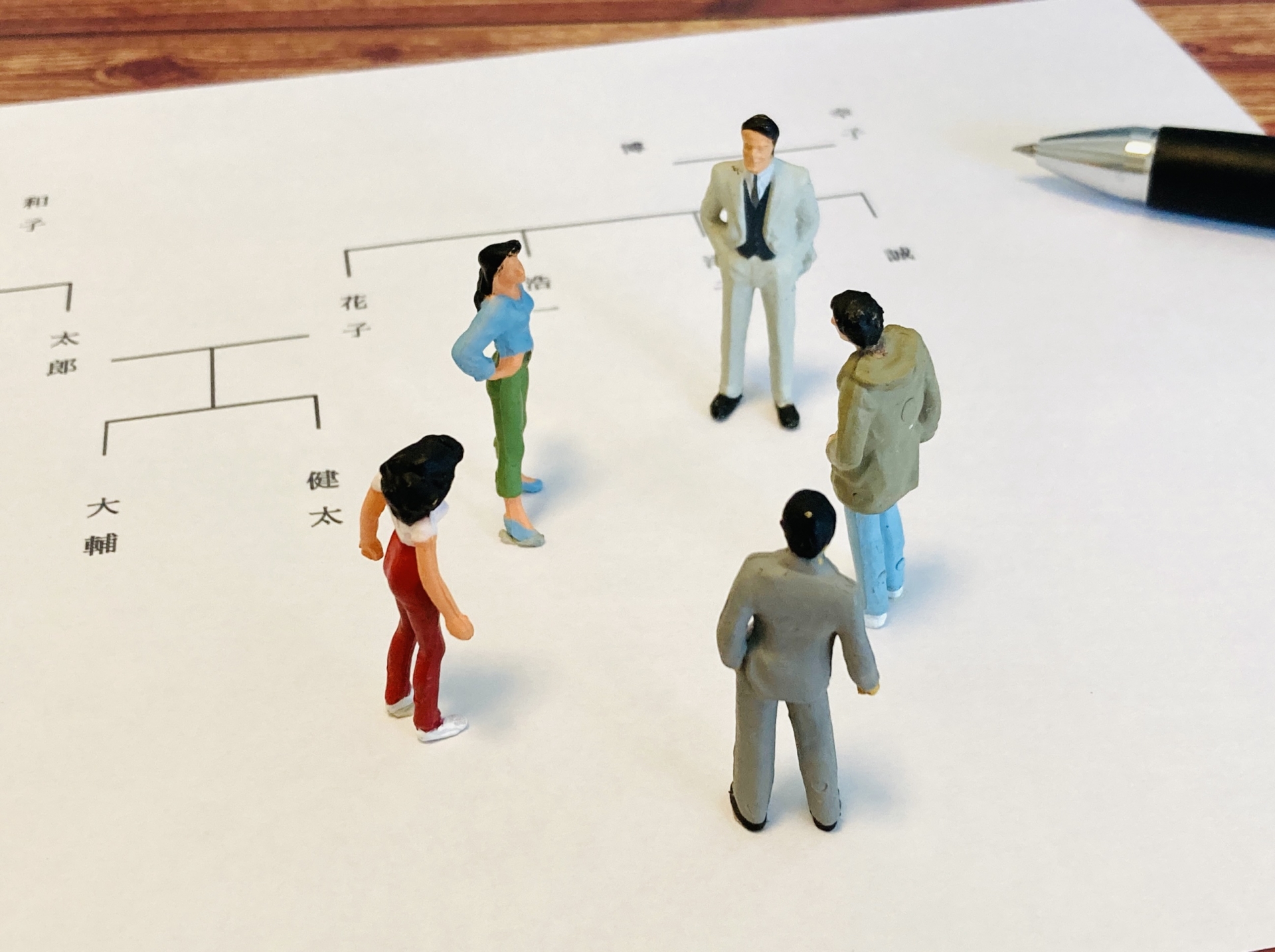
親の遺産を複数の子が相続する際、「誰がどれだけ受け取るか」、兄弟姉妹間で揉めるケースは少なくありません。トラブルを防ぐには、相続のルールや分け方の基本を知っておくことが大切です。
この記事では、この場合の法定相続分の考え方や、よくある争いを避けるためのポイントをわかりやすく解説します。
目次
親の遺産相続を複数の子(兄弟姉妹)でする場合のルールとは

親の遺産を相続する際は、基本的なルールを正しく理解しておくことが大切です。ここでは、相続人となる範囲や順位、遺産を分ける割合について詳しく解説します。
法定相続の範囲と順位
親の遺産を相続する際、最優先の法定相続人は配偶者と子どもです。配偶者は常に相続人となり、子どもがいれば配偶者と一緒に遺産を分け合うことになります。つまり、親の子どもは第一順位の相続人となります。
また、子どものうち誰かが既に亡くなっている場合でも、その子どもや孫が代襲相続するケースも。なお、被相続人である親の配偶者が既に死亡している場合は、子どもだけで相続することになります。
子どもが遺産相続する場合の割合
子どもが親の遺産を相続する場合、原則として相続分は平等に分割されます。例えば子どもに兄弟姉妹が3人いれば、それぞれ1/3ずつ分けるのが基本です。ただし、兄弟姉妹のうち亡くなったものがいるときに、その子どもがいる場合は、代襲相続によってその子が親の取り分を引き継ぎます。
なお、その人に子どもがいなければ代襲相続は発生せず、残った兄弟姉妹で均等に分けることになります。異母・異父の兄弟姉妹が混在している場合には相続分に差が出ることもあるため注意が必要です。なお、遺言書がある場合はその内容が優先されます。
親の遺産相続を子どもら(兄弟姉妹)がする場合の具体例

親の遺産を相続する際は、配偶者の有無や家族構成によって分け方が変わります。ここでは、実際に起こりうる2つのパターンについて、具体的な割合とともに見ていきましょう。
親の配偶者と子どもらで相続するケース
親の一方が亡くなり、もう一方の親が健在で、子どもたち(兄弟姉妹)も相続人となる場合、相続財産はまず配偶者が1/2を取得します。残りの1/2を、子どもたち全員で均等に分ける仕組みです。子どもの人数が多いほど、一人あたりの相続額は少なくなります。
【親の配偶者と子どもら(兄弟姉妹)で相続するケースの例】
| 相続人 | 法定相続分 | 相続額(3,000万円の場合) |
|---|---|---|
| 母または父 | 1/2 | 1,500万円 |
| 長女 | 1/4 | 750万円 |
| 長男 | 1/4 | 750万円 |
子どもらのみで相続するケース
両親ともに他界していて、相続人が子どもら(兄弟姉妹)だけの場合は、遺産を均等に分けるのが原則です。人数が多ければ一人あたりの割合は少なくなりますが、分割方法としては比較的シンプルで分かりやすいケース。
【兄弟姉妹が遺産相続するケースの例】
| 相続人 | 法定相続分 | 相続額(3,000万円の場合) |
|---|---|---|
| 長女 | 1/3 | 1,000万円 |
| 長男 | 1/3 | 1,000万円 |
| 次男 | 1/3 | 1,000万円 |
親の遺産相続を子どもらでする際にトラブルが起こりやすいケース
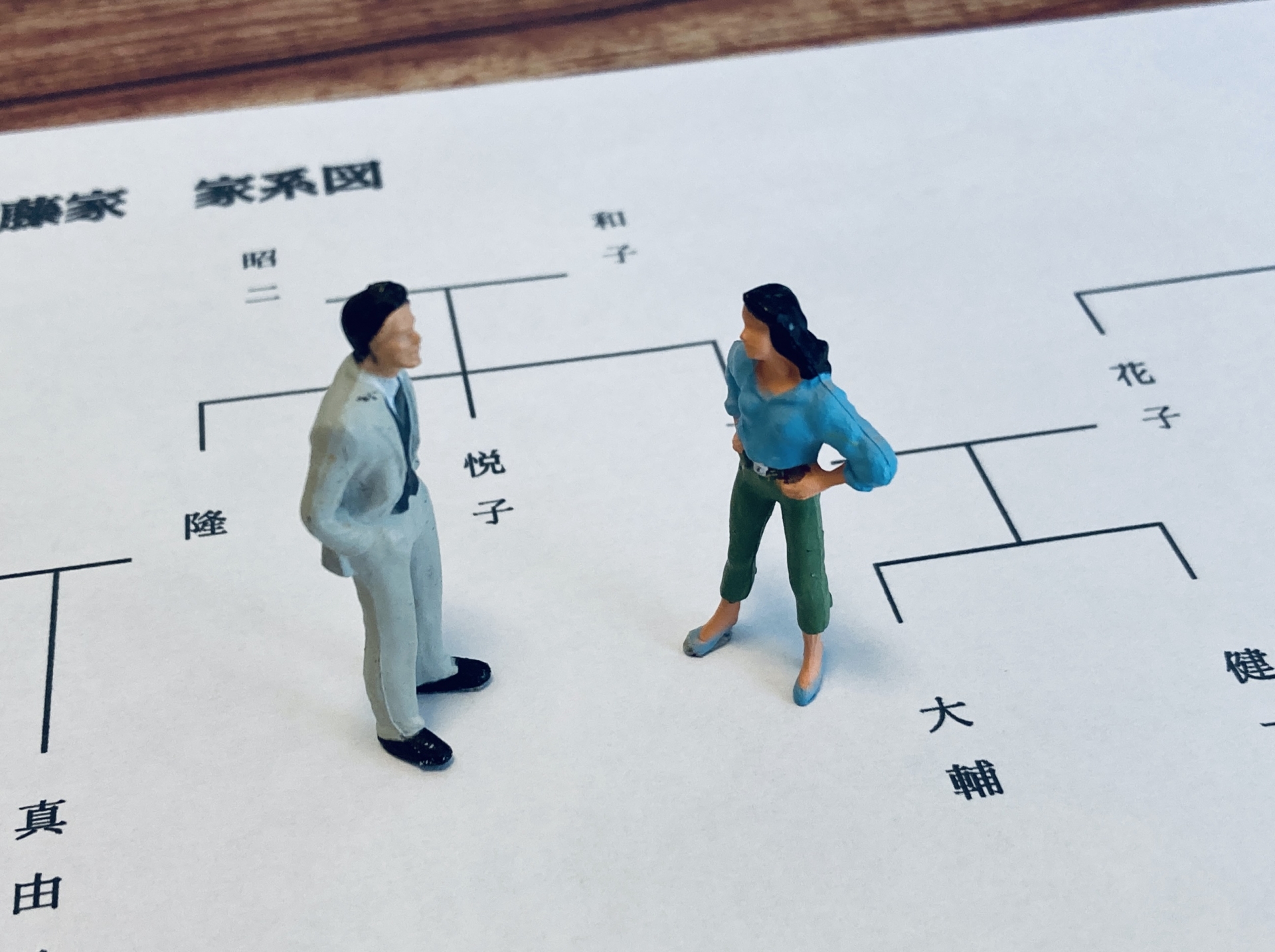
親の死後、遺産を子どもら(兄弟姉妹)で分ける場面では、考え方の違いやこれまでの関係性が影響し、トラブルが生じることも少なくありません。ここでは、実際によくある4つのケースを取り上げ、注意すべきポイントを解説します。
一部の子どもだけが親の介護や面倒を見ていた場合
親の介護を一手に担っていた兄弟が「自分は他の兄弟姉妹より多く相続すべき」と考える一方で、他の兄弟姉妹が納得できず気まずくなるケースは多くあります。特に、介護にかけた時間や精神的な負担は金銭に換算しにくく、話し合いが感情的になることも。
こうした寄与を認めてもらうには、介護内容や期間、出費を記録として残し、客観的に説明できるよう備えることが大切です。介護していた側の思いを丁寧に伝え、理解を得ながら進めましょう。
相続財産の扱いをめぐって意見が食い違う場合
遺産の多くを不動産が占める場合、現物分割するか、売却して分けるかで意見が割れることがあります。とくに「実家に住み続けたい人」と「現金化したい人」の間では対立が起きやすく、遺産分割が進まない原因になりがち。
このような場合は、換価分割(売却して分配)や代償分割(取得者が他の相続人に金銭を支払う)など柔軟な方法を検討することが重要です。
連絡が取れない・非協力的な兄弟姉妹がいる場合
相続手続きには相続人全員の合意が必要な場面が多く、連絡が取れない兄弟姉妹や非協力的な相続人がいると、大きな障害になります。絶縁状態で音信不通、または話し合いに全く応じないなどのケースでは、他の相続人にとって大きなストレスとなるでしょう。
そうした場合には、家庭裁判所を通じた対応や、弁護士への早期相談が現実的な選択肢となります。
生前に援助を受けていた兄弟姉妹がいて不公平に感じる場合
子どもの中に、親からの援助や贈与を多く受けていた人がいると、「自分たちより得をしている」との不満が生まれやすくなります。これは「特別受益」として遺産分割時に調整されることがありますが、金額・目的・証拠の有無によって判断が分かれます。
確証のないまま指摘すると感情的な衝突につながるため、冷静に事実を確認しながら丁寧に話し合う姿勢が大事です。
親の遺産相続を兄弟姉妹でする際にトラブルを防ぐポイント

親の遺産を兄弟姉妹で相続する場面では、感情的なすれ違いや価値観の違いからトラブルに発展することもあります。ここでは、できるだけ円満に相続を進めるために意識しておきたい3つの対策を紹介します。
親に遺言書を書いてもらう
兄弟間でのトラブルを避ける上で効果的なのが、親に遺言書を残してもらうことです。誰に何を相続させるかが明確にされていれば、遺産分割協議が不要になるケースもあり、相続人同士の衝突を減らすことができます。
特に、不公平感のない内容にすることで、よりスムーズな手続きが期待できます。親が元気なうちに話し合いの場を設け、遺言書の作成について前向きに検討してみるとよいでしょう。
生前に財産内容や管理ルールを共有しておく
相続をきっかけに「財産が少なすぎる」「隠し財産があるのでは」といった不信感が芽生えることも、兄弟姉妹間のトラブルを招く一因になります。こうした事態を防ぐためには、親が元気なうちから財産内容や管理方法について家族で共有しておくことが大切です。
また、誰が財産を管理するのか、介護などの役割分担をどうするのかといったルールも明確にしておくと、相続発生後の混乱を避けやすくなります。
生命保険を活用して分配トラブルを回避する
遺産の中に不動産が含まれているなど、現物を公平に分けるのが難しい場合には、生命保険を活用するのも有効な手段です。保険金は受取人の固有財産となるため、遺産分割協議を経ることなく指定された人に渡ります。
現金でバランスをとる方法として、特定の兄弟に公平な取り分を持たせたい場合などに活用できます。ただし、受取人の指定ミスなどが起きないよう、事前の確認はしっかり行いましょう。
親からの遺言で遺産相続がなかった場合の兄弟姉妹の遺留分について

親が遺言書を残し、子どものうちの誰かが遺産を全く相続できなかったとしても、「遺留分」という権利が法律上認められています。
遺留分とは、たとえ遺言によって相続から排除されていた場合でも、一定の法定相続人が最低限の取り分を主張できる制度です。
配偶者と子どもが相続人の場合、子ども全体で遺産の1/4、配偶者がいない場合は全体で遺産の1/2が遺留分となります。遺留分が侵害されていると感じた場合は、「遺留分侵害額請求」を行うことで、他の相続人や遺言で財産を受け取った人に対して金銭で請求することが可能。
遺言書の内容が不公平に思えても、冷静に法律に基づいた対応を取ることが大切です。
兄弟姉妹で遺産相続トラブルになりそうなときは専門家に相談を

親の遺産を相続する際は、ルールの理解と事前の対策がトラブル回避の鍵になります。兄弟姉妹でもめることのないよう、感情的な対立を避けるためにも、遺言書の作成や専門家への相談を活用しながら、家族で納得できる相続を目指しましょう。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。







