遺留分とは?相続トラブルを防ぐために知っておきたい基礎知識と対策
2025.07.20

遺留分とは、一定の法定相続人に最低限保障された遺産取得の権利を指します。簡単に言えば、「この分だけは必ず相続できる」と主張できる取り分のことです。
相続では遺言や生前贈与によって特定の人に財産が偏るケースがあり、遺された人がトラブルや不安に陥る可能性も。
この記事では、遺留分の基本知識と、請求方法などについて解説します。
目次
遺留分とは
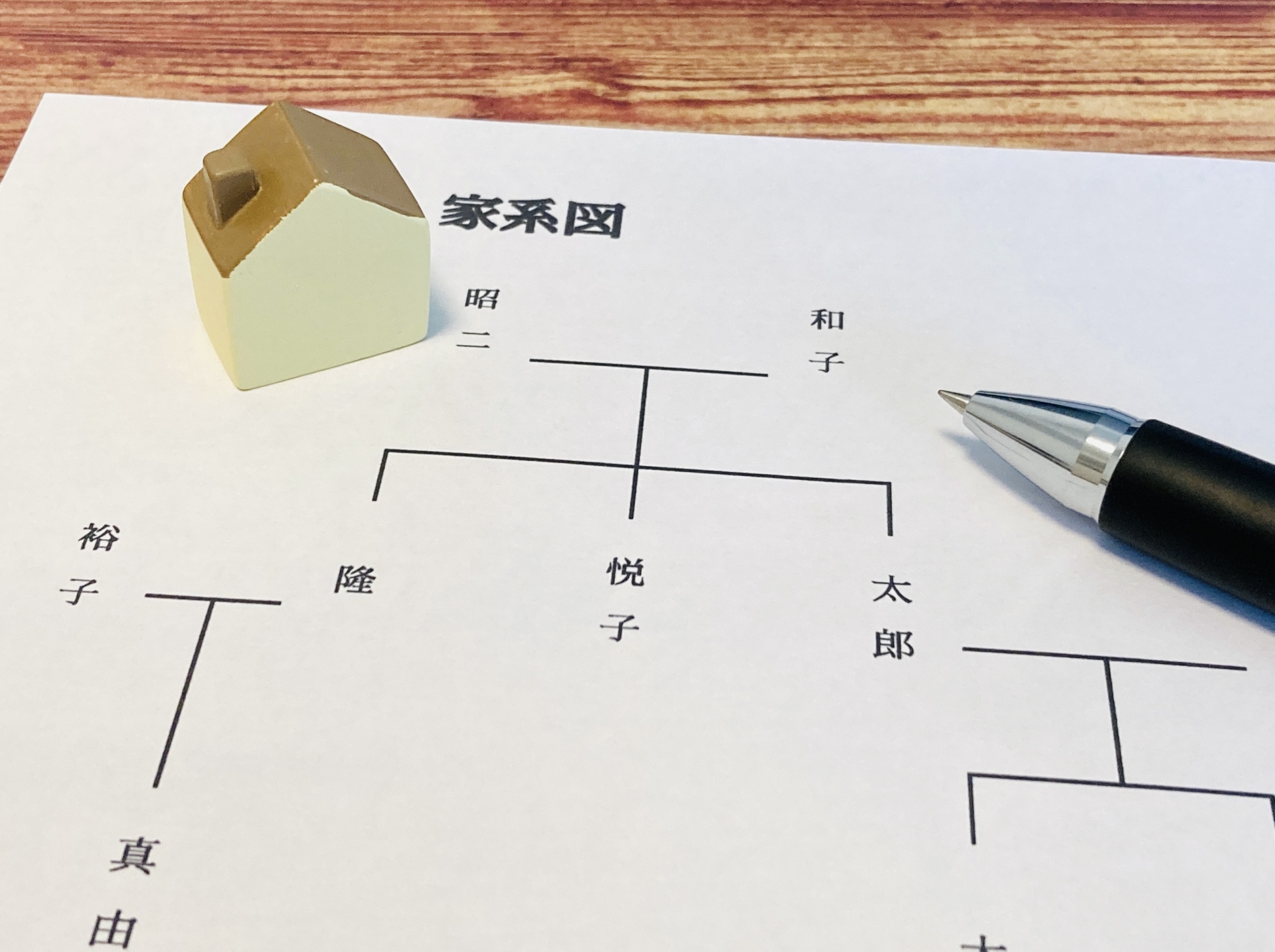
遺留分は、最低限の遺産がもらえない遺族に配慮した制度です。まずは遺留分の意味や法定相続分との違いを見ていきましょう。
一定の相続人に認められた「最低限の取り分」
遺留分とは、配偶者や子ども、親などの直系尊属といった特定の相続人に認められた「最低限の遺産取得分」です。例えば、遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書かれていても、他の相続人が遺留分を侵害された場合には、その取り分を請求できます。
この制度の目的は、相続によって遺された家族の生活が損なわれないようにすることです。なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていないため、請求することはできません。
法定相続分との違い
遺留分と混同しやすいのが法定相続分です。どちらも相続の取り分に関わるルールですが、意味合いが異なります。法定相続分は、遺言書がない場合に「誰がどれくらい相続するか」の割合が民法で定められていますが、この割合は遺産分割協議や遺言によって変更できます。
一方、遺留分は、たとえ遺言書で排除されたとしても法律で守られている「最低限の権利」です。侵害された場合には、金銭でその分を取り戻すことが可能です。
つまり、法定相続分は目安、遺留分は守られる権利という位置づけになります。
| 比較項目 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 目的 | 相続割合の基準 | 最低限の遺産取得を保障 |
| 強制力 | なし(協議・遺言で変更可) | あり(請求で回復可能) |
| 取得の方法 | 自動的に分配される | 請求しないと得られない |
遺留分の対象になる財産

遺留分を請求できるのは、単に遺言で指定された財産だけではありません。贈与や契約によって移転された財産も含まれる場合があります。ここでは、具体的にどのような財産が遺留分の対象になるのかを見ていきましょう。
遺贈された財産
遺贈とは、被相続人が遺言書によって特定の人に財産を譲り渡す行為をいいます。例えば、「自宅を配偶者に遺す」「預金を知人に贈る」といったケースが該当。遺言書によって相続人以外に財産を渡す場合でも、他の法定相続人の遺留分を侵害しているときは、遺留分侵害額請求の対象になります。
死因贈与された財産
死因贈与とは、生前に交わした契約によって、贈与者の死亡という不確定期限が到来したときに財産を移転する贈与方法です。遺贈と似ていますが、死因贈与は贈与する側ともらう側の合意が必要(契約)という点が異なります。死因贈与によって移転された財産も、相続人の遺留分を侵害している場合には請求対象となります。
生前贈与された財産
生前贈与された財産も、一定の条件を満たす場合には遺留分の請求対象になります。基本的には相続開始前1年以内に行われた贈与が対象ですが、贈与者と受贈者の双方が「遺留分を侵害していることを認識していた」場合は、1年以上前の贈与でも対象になることがあります。
さらに、法定相続人への生前贈与が特別受益にあたる場合は、原則として過去10年以内の贈与について遺留分請求が可能です。
ただし、中小企業の株式や事業用資産など、事業承継を目的とした贈与については、一定の要件を満たすことで遺留分の対象外とする特例が認められています。これらは専門的な判断が必要になるため、該当する場合は専門家に相談することをおすすめします。
遺留分を請求できる権利がある人の範囲と割合
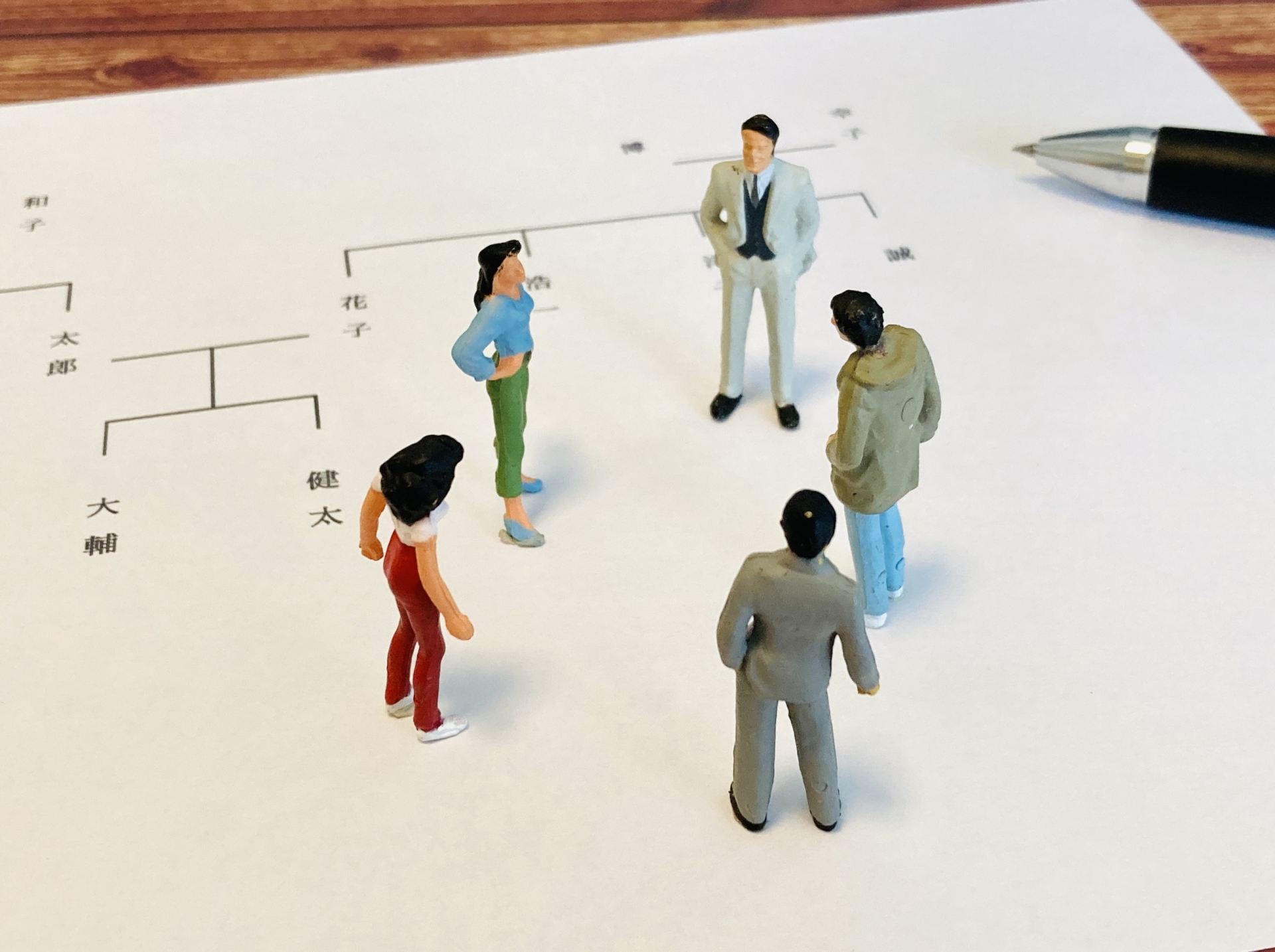
遺留分は、すべての相続人に認められているわけではありません。ここでは、誰が遺留分を持ち、どのように割合が決まるのかを解説します。
遺留分を有するのは配偶者、子、直系尊属
遺留分を請求できるのは、配偶者、子ども(または代襲相続人である孫)、そして親や祖父母などの直系尊属に限られます。この制度は、遺された家族の最低限の生活を保障することを目的としていて、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
また、相続人の立場によって、遺留分の割合は異なるため注意が必要です。代表的な相続パターン別の遺留分割合は次のとおり。
| 相続人の組み合わせ | 全体の遺留分割合 | 各相続人の遺留分割合 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 2分の1 | 配偶者:2分の1 |
| 子どものみ | 2分の1 | 子ども:2分の1 |
| 配偶者+子ども1人 | 2分の1 | 配偶者:4分の1、子ども:4分の1 |
| 配偶者+親 | 2分の1 | 配偶者:3分の1、親:6分の1 |
| 親のみ | 3分の1 | 親:3分の1 |
| 兄弟姉妹のみ | なし | 兄弟姉妹:遺留分なし |
遺留分の金額は、(相続財産額)×(遺留分の全体割合)×(法定相続分)の計算式で求めます。例えば、相続財産が5,000万円で、相続人が配偶者と子ども1人の場合、それぞれの遺留分は5,000万円×1/2×1/2=1,250万円となります。
二次相続での影響も考えておこう
二次相続では、一次相続以上に法律関係が複雑になりやすく、感情的な対立も激しくなる傾向があります。二次相続とは、最初の親の死亡による相続(一次相続)に続き、もう一方の親が亡くなったことで発生する二度目の相続を指します。
単なる2回目の相続というだけではなく、一次相続で分割されなかった財産や遺留分の問題が引き継がれるため、法的な処理が煩雑になりやすいのが特徴です。
【具体例(父・母・息子2人の家族の場合)】
- 1.父が亡くなり、母と息子2人が父の遺産を相続(一次相続)
- 2.父の遺産分割が終わらないうちに母も死亡(二次相続)
- 3.この結果、父と母それぞれの相続問題が同時に発生し、息子2人で両方を解決しなければならなくなる
さらに、両親という仲裁役がいない中、兄弟間だけで遺産分割を進めるため、利害がぶつかりやすく感情的なもめごとに発展しやすい状況になります。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、早い段階で相続の専門家に相談し、全体の設計を考えておくことが重要です。
遺留分を請求できない人
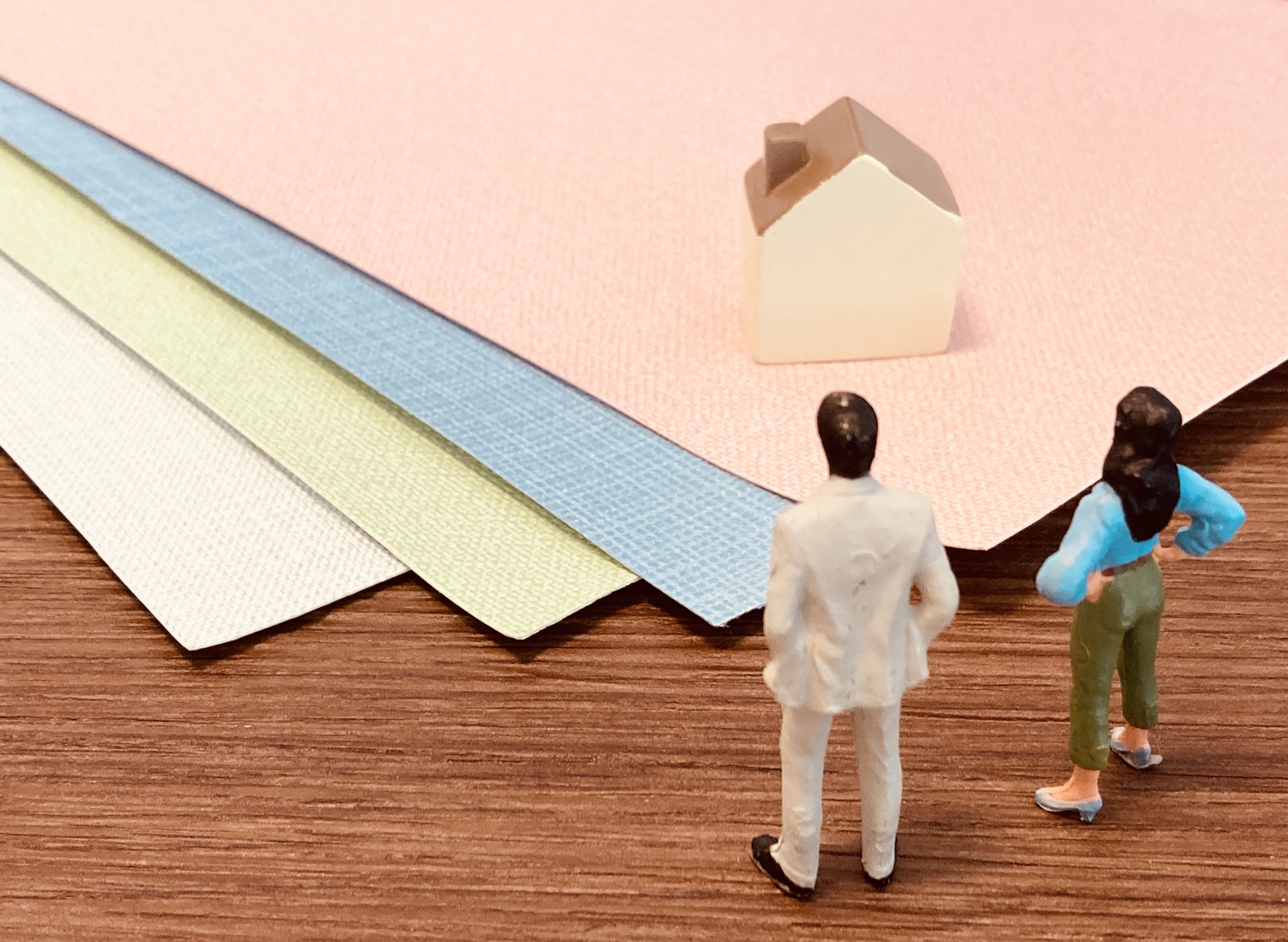
遺留分は原則、配偶者や子ども、親などに保障されますが、すべての相続人に認められるわけではありません。次のケースでは、遺留分を請求できなくなります。
【遺留分を請求できない主なケース】
・相続欠格者
被相続人を殺害した、または遺言書の偽造・隠匿など重大な不正行為をした人
・相続廃除された人
虐待や著しい非行が原因で、被相続人から相続権を剥奪された人
・相続放棄をした人
家庭裁判所で正式に相続放棄手続をした場合、初めから相続人ではなかったとみなされる
・遺留分を放棄した人
家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄した場合、権利は消滅する
遺留分を侵害された場合はどうする?
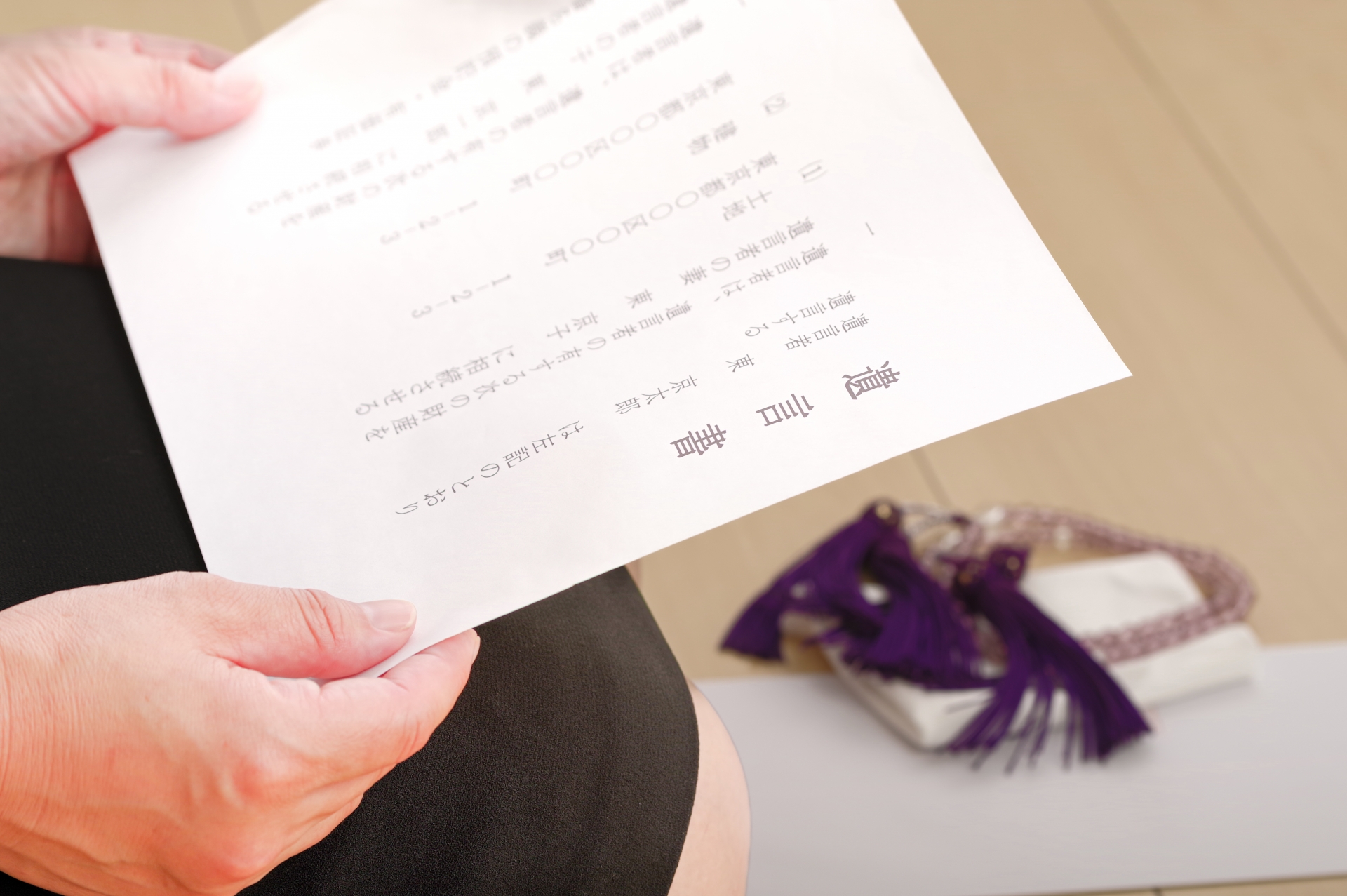
遺言や生前贈与によって、遺留分が侵害されてしまうことは珍しくありません。そんなとき、遺留分を持つ相続人は「遺留分侵害額請求」という法的な手続きによって、侵害分の回復を求めることが可能です。
ここでは、請求できる人やその流れ、そして注意すべき期限について解説します。
相続人であれば遺留分侵害額請求ができる
遺留分を侵害された場合、配偶者・子ども・親などの相続人は「遺留分侵害額請求」によって、その不足分を金銭で取り戻せます。
2019年の民法改正前は、遺産そのものを返還させる「遺留分減殺請求」が主流でしたが、不動産や株式が共有状態になるなどトラブルが起きやすい制度でした。改正後は、現物ではなく金銭で清算する方式へと変わったことで、よりシンプルかつ実務的な解決が可能に。
ただし、権利があるだけで、自動で遺留分が戻ってくるわけではないため、請求する側が自ら行動を起こす必要がある点には注意が必要です。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求は次のステップで進めます。
- 1.相続人の確定と財産調査を行い、自分の遺留分を計算する
- 2.侵害した相手に通知し、話し合いを試みる
- 3.交渉がまとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てる
- 4.解決しない場合は訴訟へ移行する
遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求には時効があり、一定期間を過ぎると請求できなくなってしまいます。
期限は次のどちらかが適用されます。
- ・遺留分侵害を知った日から1年以内
- ・相続開始から10年以内(侵害を知らなかった場合でも)
交渉が長引いている間に時効を迎えるケースも少なくありません。少しでも「遺留分が侵害されているかもしれない」と思ったら、早めに弁護士や専門家に相談することをおすすめします。
遺留分でもめないためにできる対策

相続は金銭だけではなく感情も絡むため、遺留分を考えた生前対策が重要です。もめごとを回避するために、以下のような対策を事前に検討しておきましょう。
【遺留分トラブルを防ぐための主な対策】
1.遺言書を作成する
遺留分を意識した内容で遺言を残しておくと、相続人同士の認識違いを防げる
2.家族間で生前に話し合っておく
本人の意思と家族の希望をすり合わせておくことで、後のトラブルを防止する
3.専門家(弁護士・税理士など)に相談する
法律や税務の観点から最適な対策を設計できる
遺留分とは遺された人に配慮した制度

遺留分とは、遺された配偶者や子ども、親などに最低限の遺産取得を保障するための制度です。被相続人の意思を尊重しつつも、相続人の生活を守る仕組みといえます。
相続でもめないためには、遺留分の基本を理解し、生前からの対策を考えておくことが大切です。家族の絆を守るためにも、早めの準備を心がけましょう。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。





