相続放棄とは?手続きの流れや必要書類、注意点をわかりやすく解説
2025.07.20
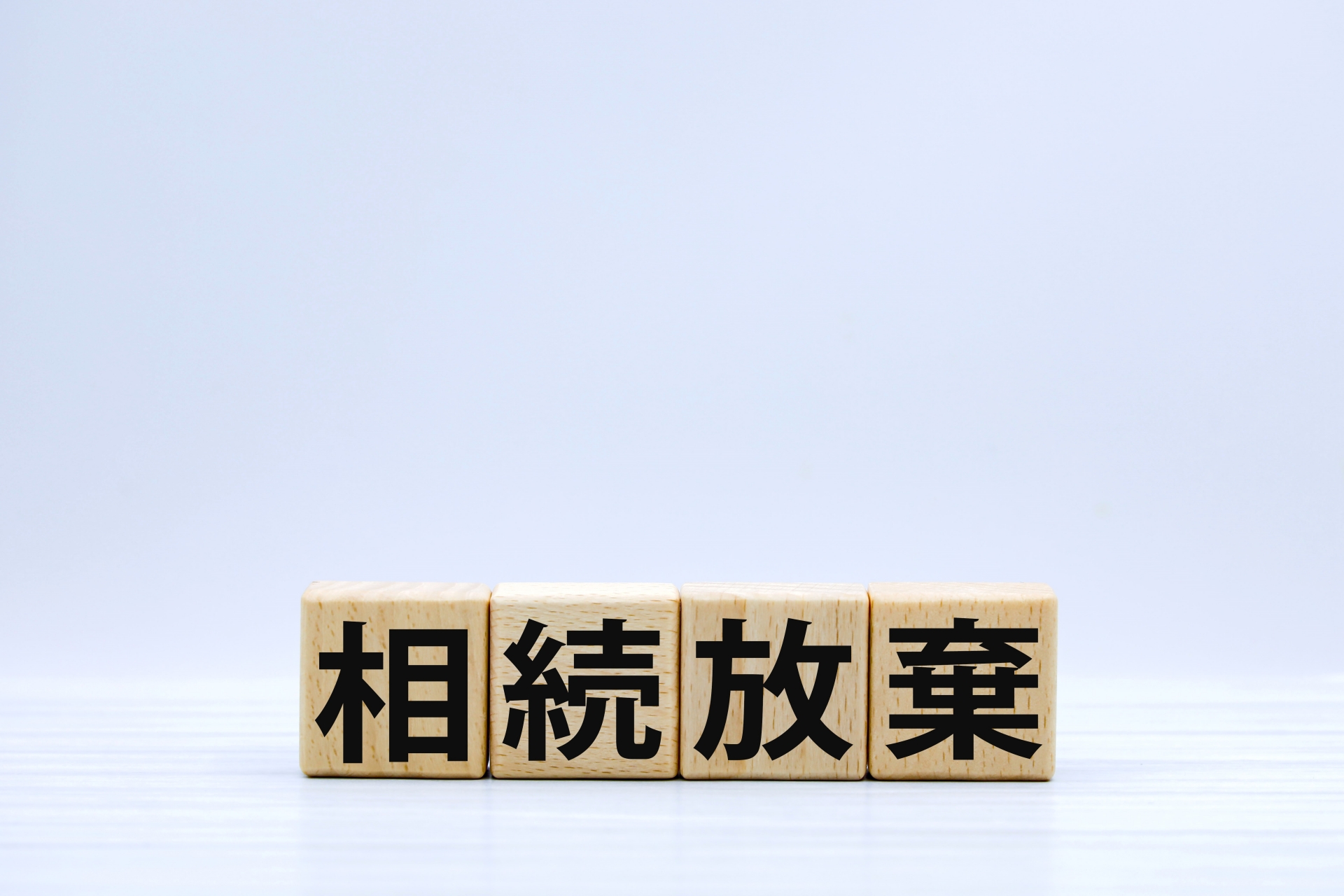
相続放棄とは、相続人が財産も負債も引き継がない選択をすることです。特に、借金などの負債がある場合に有効ですが、手続きを誤ると放棄できなくなるリスクもあります。
本記事では、相続放棄の基本から手続きの流れ、必要書類、注意点までわかりやすく解説。3ヵ月以内の申請期限や、放棄ができないケースについても詳しく紹介します。
目次
相続が発生した際は3つの方法を選択できる

相続が発生した際、相続人には次の3つの選択肢があります。
| 選択肢 | 特徴 |
|---|---|
| 単純承認 | すべての財産(プラス・マイナス)をそのまま相続する |
| 限定承認 | 相続財産の範囲内で負債を支払う |
| 相続放棄 | 財産も負債も引き継がない |
相続の方法によって影響が異なるため、早めに遺産の状況を確認し、専門家に相談しながら慎重に判断するのがおすすめです。今回は、相続放棄について詳しく解説します。
相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が財産も借金も受け継がず、相続人としての立場を失う制度です。ここでは相続放棄の概要や、財産放棄との違いについて解説します。
相続人が財産も負債も引き継がないこと
相続放棄とは、相続人が財産も負債も引き継がないことを決め、法的に相続人の資格を失う手続きのことです。相続放棄をすることで、相続人としての権利や義務がなくなります。
借金や債務の返済義務も負わなくて良いのがメリットですが、相続放棄には期限があります。期限を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなるため、早めに判断することが重要です。
財産放棄との違い
相続放棄と財産放棄は混同されがちですが、法的な意味が異なります。相続放棄をすると相続人の地位を完全に失い、遺産分割協議に関わることもできず、財産も負債も相続しません。
一方で、財産放棄は相続人の地位を保ったまま、特定の財産を受け取らない意思を示す行為です。遺産分割協議で合意すれば放棄が成立し、撤回も可能。ただし、財産放棄では相続人の地位が残るため、負債の相続義務は免れないという点に注意が必要です。
相続放棄の手続きについて

相続放棄を行うには、期限や手続きの流れ、必要書類を正しく把握しておくことが大切です。ここでは、相続放棄の具体的な進め方と注意点を解説します。
相続放棄の申請期限は3ヵ月以内
相続放棄の申請は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ行う必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなります。
ただし、正当な理由(財産調査に時間がかかる、相続の事実を知るのが遅れた等)があれば、家庭裁判所へ申請し、期間の延長を認めてもらうことも可能。期限内に必要書類を揃えられなければ手続きが無効になるため、早めの準備が重要です。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、家庭裁判所への申述を経て正式に認められる手続きです。次の流れで進めていきます。
- 1.被相続人の死亡を確認し、財産の状況を調査する
- 2.相続放棄の意思を固め、必要書類を準備する
- 3.被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する
- 4.裁判所からの照会書に回答する
- 5.相続放棄の許可が下りたら「相続放棄申述受理通知書」を受け取る
債権者などから借金の支払いを求められた場合に備え、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を取得しておくと便利です。必要に応じて弁護士や司法書士に相談しながら、適切に対応しましょう。
相続放棄の必要書類
相続放棄を行うには、家庭裁判所へ申述書と必要書類を提出する必要があります。書類は申述人の立場によって異なるため、事前に確認して準備しましょう。
| 分類 | 必要書類 |
| 共通 | 相続放棄申述書(裁判所指定のフォーマット) 被相続人の住民票除票または戸籍附票 申述人の戸籍謄本 |
| 配偶者 | 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本 |
| 子・孫(第一順位相続人) | 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本 代襲相続人(孫、ひ孫など)の場合: 被代襲者(本来の相続人)の死亡が記載された戸籍謄本 |
| 父母・祖父母(第二順位相続人) | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 死亡した者がいる場合:その戸籍謄本 相続人より下の代の直系尊属(例:父母)が死亡している場合: その死亡が記載された戸籍謄本 |
| 兄弟姉妹・甥姪(第三順位相続人) | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 直系尊属(父母など)の死亡が記載された戸籍謄本 申述人が代襲相続人(甥・姪)の場合: 被代襲者(本来の相続人)の死亡が記載された戸籍謄本 |
必要書類は家庭裁判所のホームページでも確認できます。
相続放棄のデメリットと注意点
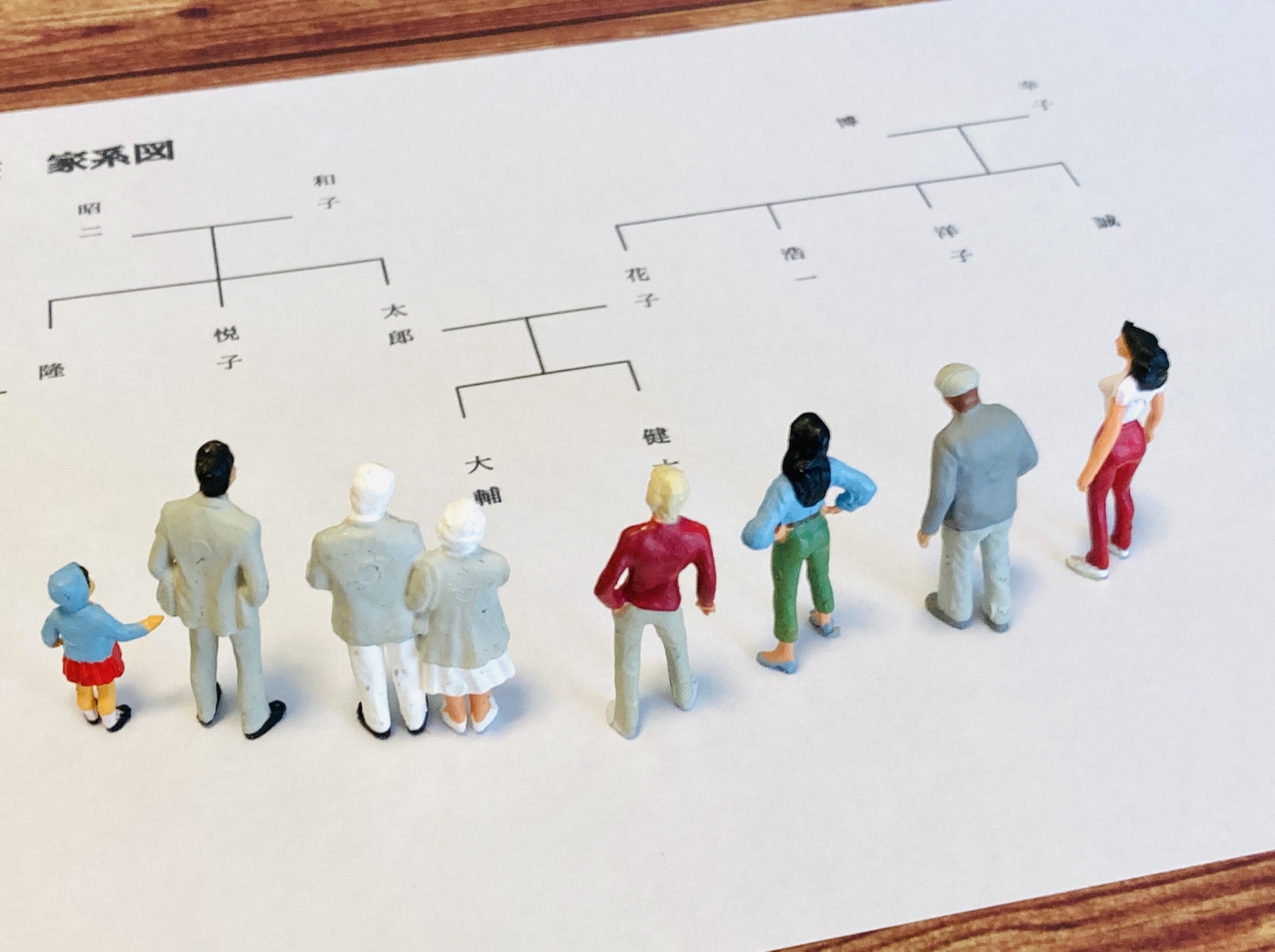
相続放棄にはメリットだけではなく、注意すべきデメリットもあります。ここでは、放棄後に発生する義務やトラブルの可能性、撤回できないリスクについて解説します。
相続放棄した後に相続財産の管理義務が発生する場合がある
相続放棄をしても、すぐにすべての責任から解放されるわけではありません。相続財産を現に占有している場合、次の管理者に引き渡すまで適切に保存する義務が発生します。
例えば、相続放棄をした人が被相続人の家に住んでいた場合、その家を相続財産清算人に引き渡すまでの間、管理義務が生じます。もしも管理を怠り、建物が倒壊して第三者に被害を与えた場合、損害賠償責任を問われる可能性も。管理義務を免れるには、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任申し立てが必要です。
財産を現に管理していない場合は義務は発生しませんが、事前に確認しておきましょう。
相続放棄をすると、次の相続順位の人に負担が移る
相続放棄をすると、次の相続順位の人に相続権が移ります。しかし、負債も引き継がれるため、事前に親族と相談しておかないと、思わぬトラブルに発展する可能性も。
亡くなった人の子が相続放棄をした場合、相続権は父母や祖父母(直系尊属)に移ります。直系尊属も放棄すれば、次に兄弟姉妹や甥姪へと移行。相続人が負債の存在を知らずに相続してしまうと、借金を背負うことになりかねません。
相続放棄を検討する際は、次に相続する可能性のある人と事前に相談し、意図しない負担が生じないように対策を立てることが重要です。
放棄の手続きを一度すると撤回できない
相続放棄は、一度家庭裁判所で認められると、原則として撤回できません。そのため、手続きをする前に被相続人の財産と負債を十分に調査する必要があります。
もしも相続放棄をした後に、多額の遺産が見つかったとしても、後から「やはり相続したい」と申し出ることはできません。慎重に判断しないと、思わぬ損失を被る可能性があります。
ただし、詐欺や強迫による相続放棄であった場合は、例外的に取り消しが認められることもあります。いずれにせよ、相続放棄は慎重に進めるべき手続きであり、不安がある場合は専門家に相談するのが安全です。
相続放棄ができないケースとは?

相続放棄を検討していても、特定の行為をすると「相続を承認した」とみなされ、放棄ができなくなることがあります。
| 条件 | 具体的な行為 |
| 相続財産を処分・使用した場合 | 預貯金を引き出して自分の口座に入れる 不動産を売却・名義変更する 遺品整理や形見分けで価値のある物を処分・譲渡する 家賃の支払いや税金の清算を被相続人の財産から行う |
| 相続放棄前に財産を管理・利用した場合 | 預金を解約して自分名義に変更する 賃貸収入の振込先を自分の口座に変更する 亡くなった人の住んでいたアパートの契約解除をする |
相続放棄を選ぶ場合は期限内の手続きを
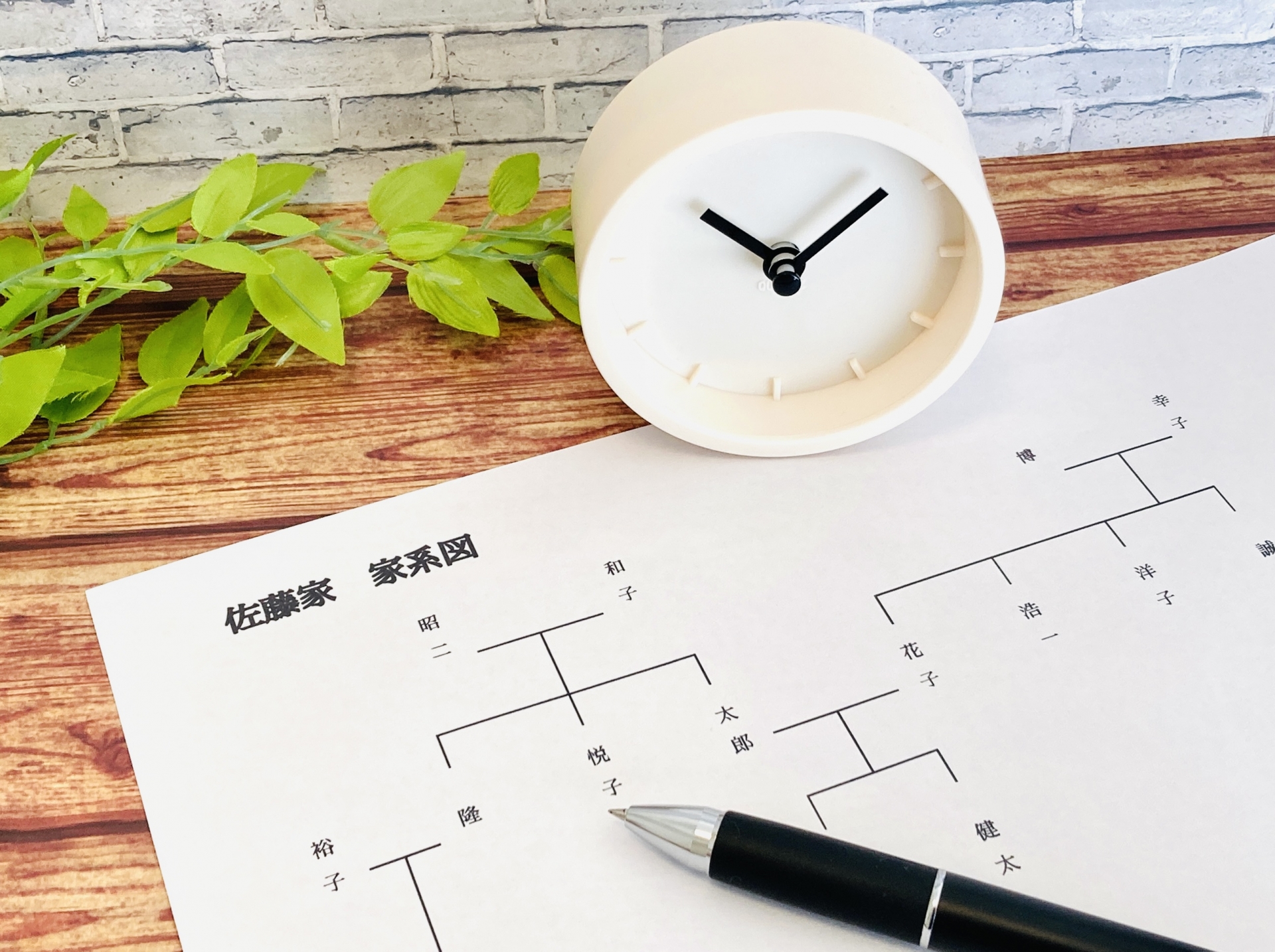
相続放棄をするには、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。期限を過ぎると放棄できず、借金などの負債を引き継ぐ可能性があるため、早めの判断が重要です。
もしも財産の処分や利用をすると、相続を承認したとみなされ、放棄が認められなくなることもあるため注意しましょう。必要書類の準備や財産調査を速やかに行い、期限内に確実に手続きを進めることが大切です。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。

