不動産を相続したら必要な手続きとは?義務化の概要・流れを解説
2025.06.18

不動産を遺産相続した際、「何から始めればいいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。令和6年4月から相続登記が義務化され、名義変更は3年以内に行う必要があります。
本記事では、相続登記の義務化の概要から、手続きの流れや費用、放置によるリスクまでをわかりやすく解説します。
目次
令和6年4月から義務化!不動産を相続する際は相続登記が必要

令和6年(2024年)4月1日から、不動産を相続した場合の相続登記が、法律で義務化されました。正当な理由なく3年以内に申請しないと、最大10万円の過料が科される可能性があります。
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を相続人の名義に変更する手続きのことです。放置すると「誰のものかわからない不動産」になり、売却や活用もできなくなるおそれがあります。
遺言書の有無や遺産分割協議の結果によって必要な書類や手続きが異なるため、できるだけ早めに対応しましょう。
不動産を相続するまでの基本的な流れ

不動産を相続するには、いくつかの手続きを順に追って進める必要があります。ここでは、相続発生から登記・申告までの基本的な流れをわかりやすく解説します。
遺言書の有無を確認し、相続手続きの方針を決める
相続手続きを始める際は、最初に遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言書があれば、基本的にはその内容に沿って相続手続きを進めるため、他の手続きを無駄にしないためにも、できるだけ早い段階での確認が求められます。
もし遺産分割協議を終えた後に遺言書が見つかった場合でも、遺言の内容が法的に優先されるため、協議をやり直す必要が出てきます。特に公正証書遺言については、公証役場での検索制度があるため、早めに調査しておくと安心です。
戸籍を収集して、相続人を正確に確定する
相続人を正しく確定するには、被相続人の戸籍を出生から死亡までさかのぼって収集する必要があります。遺言書がない場合、相続人は法律に基づいて決まるため、親子関係や婚姻歴などを正確に把握しておくことが重要です。
相続人に漏れがあると、せっかく行った遺産分割協議を一からやり直すことにもなりかねません。こうしたトラブルを避けるためにも、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を早めに揃え、丁寧に確認を進めましょう。
不動産を含めた財産を把握し、財産目録を作成する
相続財産を正確に把握するためには、不動産を含むすべての財産を整理し、財産目録としてまとめておくことが重要です。
例えば、預貯金であれば通帳や残高証明書から確認が可能。不動産については、固定資産税の課税明細書や、市区町村役場で取得できる「名寄帳」を活用すると、所有している物件の情報を把握できます。
こうした情報をもとに作成した財産目録は、遺産分割協議をスムーズに進めるだけではなく、相続税の申告や評価にも大いに役立ちます。
遺産分割協議で不動産の分け方を決める
遺言書がない場合や、内容が不明確な場合には、法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。特に不動産は分割しづらい財産であるため、誰が取得するのかを明確にし、公平性にも配慮した話し合いを行うことが大切です。
協議がまとまったら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名し、実印を押印します。この協議書は、不動産の相続登記や銀行口座の名義変更など、各種手続きに必要となるため、記載ミスや漏れがないよう注意して作成しましょう。
必要書類を集めて、不動産の相続登記をする
不動産の相続が決まったら、速やかに相続登記を行う必要があります。相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で手続きすることになっていて、遺産分割協議書や戸籍謄本、登記事項証明書などの書類を用意しなければなりません。
登記を行っていない不動産は売却や有効活用ができないため、手続きを後回しにせず、早めに対応することが重要です。
相続税がかかる場合は10ヵ月以内に申告と納付を行う
相続税が発生する場合は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告と納付を完了しなければなりません。期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される可能性があるため注意が必要です。
相続税は、不動産を含む遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた場合に課税対象となります。名義変更や遺産分割協議に時間がかかるケースもあるため、できるだけ早めに手続きを進め、必要に応じて税理士など専門家へ相談することをおすすめします。
不動産を相続登記する際にかかる費用

不動産の相続登記には、税金や書類取得などのさまざまな費用がかかります。なお、自分で行う場合と専門家に依頼する場合で金額が異なります。
| 費用項目 | 目安金額・内容 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額×0.4% |
| 必要書類の取得費 | 1〜3万円(戸籍、住民票など) |
| 不動産調査費 | 2,000〜3,000円(名寄帳、登記事項証明書など) |
| 司法書士報酬(依頼した場合) | 6〜13万円(登記のみ) |
司法書士に依頼する場合は、遺産分割協議書作成や戸籍収集などで追加費用が発生することもあります。
不動産を相続する4つの方法
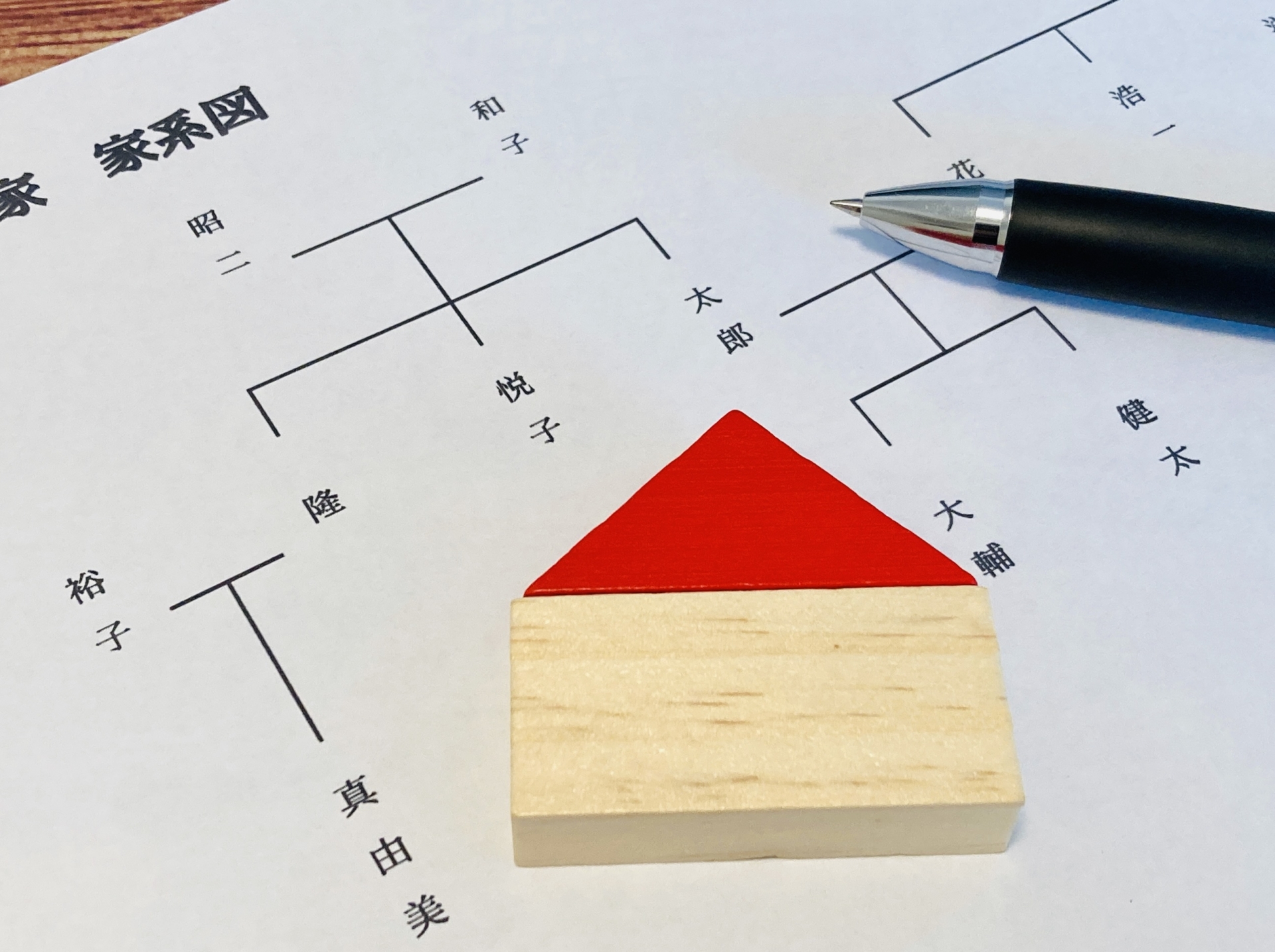
不動産の相続には複数の方法があり、状況や相続人の希望によって適した手続きが異なります。ここでは代表的な4つの相続方法と、それぞれの特徴を紹介します。
1.手続きがシンプルな「現物分割」
現物分割とは、不動産をそのままの形で相続人に分ける方法です。例えば、相続財産に2つの不動産があり、相続人がそれぞれ1つずつ相続するケースがこれに該当します。手続きが比較的シンプルで、名義変更もスムーズに行える点が大きなメリット。
ただし、相続する不動産の価値に差がある場合には、不公平感が生まれやすく、相続人同士のトラブルにつながる恐れがあるため、事前に慎重な話し合いが必要です。
2.相続の不公平を調整できる「代償分割」
代償分割は、相続人のうち1人が不動産を単独で相続し、その代わりに他の相続人へ金銭や別の財産を分け与える方法です。この方法を選ぶことで、不動産の所有者が1人となるため、売却や賃貸などの活用がしやすくなります。
ただし、代償金を支払う相続人には、それなりの資金力が必要となるため、資金準備の見通しが立っていることが前提となります。
3.売却して現金で分ける「換価分割」
換価分割は、不動産を売却して得た現金を相続人で分ける方法です。現金で分配することで、平等な相続が実現しやすく、不公平感が出にくいのが特徴。
ただし、不動産の売却には時間がかかる場合もあり、売却までの間に発生する固定資産税や維持費を誰が負担するのかを事前に決めておく必要があります。また、相続人の中に実際にその不動産に住んでいた人がいる場合は、その人への配慮も必要です。
4.慎重な判断が必要な「共有名義」
共有名義とは、複数の相続人が1つの不動産を共有する方法です。それぞれの持分割合を決めて登記することで形式上は公平に見えますが、実務では注意が必要。
不動産を売却したり賃貸したりする際には、共有者全員の同意が必要になるため、意思決定がスムーズに進まないこともあります。さらに、共有者が亡くなると、その持分がさらに細かく相続されていくため、不動産の権利関係が複雑化し、将来的なトラブルの原因となる可能性もあります。
相続税の計算にも必要!不動産の評価方法

不動産を相続する際には、その評価額を正しく把握することが重要です。ここでは、相続税の計算にも関わる不動産の評価方法について、土地と建物それぞれの評価方法を見ていきましょう。
土地の評価は「路線価方式」か「倍率方式」で決まる
土地の評価は、相続税を正しく計算するうえで非常に重要なポイントです。評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があり、地域によって適用される方式が異なります。
「路線価方式」は、国税庁が毎年公表している路線価をもとに評価額を算出する方法。主に都市部や市街地で用いられます。例えば「200A」と表示されている場合、その土地の1平方メートルあたりの評価額は20万円です。
評価額の算出には、路線価に奥行価格補正率などの各種補正率をかけ、さらに土地の面積を乗じる必要があります。借地権がある場合は、「A〜G」で示された借地権割合も加味されるでしょう。
一方、「倍率方式」は、路線価が設定されていない地域で採用される方法で、固定資産税評価額に国税庁が定めた倍率をかけて計算します。評価倍率や固定資産税評価額は、納税通知書や国税庁の「路線価図・評価倍率表」で確認可能です。
建物(家屋)の評価は固定資産税評価額で確認できる
建物(家屋)の評価については、固定資産税評価額がそのまま相続税の評価額として用いられます。固定資産税評価額は、毎年送付される課税明細書に記載されていて、手元に通知書がない場合でも、市区町村の役所や都税事務所などで確認することが可能です。
相続した不動産を放置するとどうなる?

不動産を相続したら、そのまま放置せず、早めに活用方法を検討することが重要です。
住む・貸す・売却などの選択肢がある一方で、何も手をつけずに放置してしまうと、固定資産税の負担が続くだけではなく、老朽化による倒壊や雑草・害虫による近隣トラブルの原因にもなります。
また、「空き家の特例」などの税制優遇が受けられなくなる可能性もあるため注意が必要です。活用が難しい場合や不要な場合は、相続放棄を含めて検討することもひとつの選択肢です。管理が困難であれば、早期の売却や専門家への相談も視野に入れましょう。
不動産の相続は3年以内に行おう

相続登記の義務化により、不動産の相続は「いつかやればいい」では済まされなくなりました。この記事で紹介した流れや費用、評価方法を参考に、トラブルを防ぐためにも3年以内を目安に計画的に手続きを進めましょう。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。







