相続時精算課税制度とは?必要な準備や手続き、改正内容など解説
2025.05.21

相続時精算課税制度は、2,500万円までの贈与に対する贈与税を軽減できる便利な制度です。しかし、制度が複雑でどこから始めたらいいのか、悩んでしまう人も多いのではないでしょうか。
この制度を上手に活用するためには、適用条件や利用方法、注意点をしっかりと理解しておくことが大事です。本記事では、相続時精算課税制度の概要や実際の利用方法、計算式などをわかりやすく解説します。
目次
相続時精算課税制度とは

この章では、制度の概要、必要書類、贈与税の計算式、適用条件を詳しく解説します。相続時精算課税制度を賢く活用し、将来の相続税負担の軽減に役立ててください。
子や孫への生前贈与について選択できる制度
相続時精算課税制度は、2,500万円までの贈与に対しての贈与税が非課税となり、贈与者が亡くなった際に、贈与された財産と相続財産の合計額を基に相続税を算出し、一括で納税する制度です。
贈与財産の種類や回数に制限はなく、金額にのみ上限があります。令和6年からはこれに加えて、年間110万円までの贈与も非課税になる基礎控除が新たに加わりました。この基礎控除は、相続財産に加算されないため、より柔軟な資産移転が可能になります。
生前贈与を活用しながら、将来の相続税負担を見据えた計画的な資産承継ができるのが大きな特徴です。
適用対象者
相続時精算課税制度は、以下の条件を満たす贈与者と受贈者に適用されます。
贈与者:60歳以上の父母または祖父母
受贈者:18歳以上の子や孫(推定相続人)
制度を利用する際は、これらの要件を満たしているか事前に確認し、適切に活用しましょう。
暦年贈与との違い
贈与税の非課税措置は、暦年課税制度にも導入されています。
暦年贈与は、年間110万円までの贈与が非課税となり、毎年少しずつ贈与することで節税ができる制度です。しかし、110万円超の贈与には10~55%の累進課税がかかるため、計画的に行うことが重要です。
一方、2,500万円まで非課税の相続時精算課税制度は、超過分一律20%課税。2024年以降は、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が追加され、少額ずつの贈与でも対応可能になりました。
ただし、相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できないため、その違いを理解した上で選びましょう。
【2024年改正】相続時精算課税制度の変更点
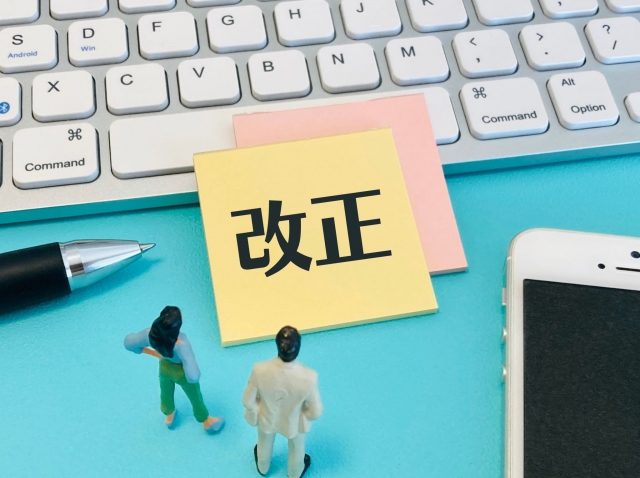
先述しましたが、税制改正により相続時精算課税制度がより活用しやすくなりました。詳しい改正内容は以下の通りです。
1.年間110万円の基礎控除の新設
- ・特別控除2,500万円とは別に、年間110万円までの非課税での贈与が可能になった
- ・110万円以下の贈与は相続財産に加算不要で、相続税もかからない
2.贈与税の申告不要
・改正前は小さい額の贈与でも申告が必要でしたが、110万円以下であれば申告が不要に変更
改正により相続時精算課税制度の利便性が向上し、贈与の選択肢が広がりました。適切に活用するには、制度の特性を理解することが重要です。
改正内容についてもっと詳しく知りたい人は以下をチェックしてみてください。
相続時精算課税制度を利用するための準備と申告方法

この章では、相続時精算課税制度を利用するための手続きについて、必要書類や贈与税の計算方法、申告の流れを、具体例を交えて説明します。制度を適切に活用するために、申告期限や提出方法もしっかり確認しておきましょう。
必要書類
相続時精算課税制度を利用する際は以下3点を準備しましょう。
- 1.相続時精算課税選択届出書
- 2.贈与申告書
- 3.受贈者の戸籍謄本
贈与税の申告書等の様式は、国税庁ホームページよりダウンロード可能です。
相続時精算課税制度の計算式
年間110万円の基礎控除と、相続時精算課税を活用した際の贈与税の計算式は以下です。
(年間贈与額-110万円の基礎控除+年間贈与額-110万円+・・・・)-2,500万円の特別控除×20%
先にも述べた通り、累計2,500万円までの贈与は非課税ですが、超えた部分には贈与税がかかります。具体例を用いて説明するので、参考にしてください。
(例1)
5年間、毎年500万円の贈与を行い、相続時精算課税制度を利用した場合
(500万円-110万円)×5年=1,950万円<2,500万円の特別控除
つまり、贈与税なし(特別控除内)
(例2)
5年間、毎年800万円の贈与を行い、相続時精算課税制度を利用した場合
(800万円-110万円)×5年=3,450万円>2,500万円の特別控除
3,450万円-2,500万円の特別控除=950万円
950万円×20%=190万円
つまり、950万円が課税対象となり、贈与税が190万円かかる
申告方法
相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告が必要です。受贈者が必要書類をそろえ、住所地の税務署へ提出します。書類は国税庁のサイトからダウンロードが可能です。
申告は窓口・郵送・e-Taxで行えます。期限内に適切に申告を行いましょう。
相続時精算課税制度の3つの注意点

相続時精算課税制度を利用する際には、3つの注意点があります。同制度を選択すると、暦年贈与と併用できず、小規模宅地等の特例も適用できません。また、贈与税の申告が必要です。適切に制度を活用するための注意点を押さえましょう。
1.暦年贈与と併用できない
相続時精算課税制度を選ぶと、同じ人からの暦年贈与は使えなくなり、途中でやめることもできません。ただし、別の人からの暦年贈与は受けられます。
制度を利用する前に、相続時精算課税制度と暦年贈与のどちらが自分に合っているか、しっかり考えて選ぶことが大切です。判断に困った場合は専門家へ相談しましょう。
2.小規模宅地等の特例が適用できなくなる
相続時精算課税制度を利用して土地を贈与すると、小規模宅地等の特例は受けられません。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たせば、土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。この特例は相続時のみ適用されるため、生前贈与した宅地に対しては適用不可となります。宅地の評価額が高い場合、特例を活用すれば相続税の大幅な節税が可能なため、制度選択を慎重に検討することが重要です。
3.贈与税の申告が必要になる
贈与税の申告が期限を過ぎると、特別控除の適用を受けることができません。贈与額が年間110万円を超える場合、申告期限は翌年3月15日までです。期限を過ぎると、贈与額の全額に一律20%の贈与税が課されるため、期限内の申告が重要となります。
ただし、生活費や教育費など常識の範囲内の支出は非課税となり、申告は不要です。
相続時精算課税制度が活かせる4つのケース

相続時精算課税制度は、条件が合えば有効に使える制度です。この章では、制度を活かせる4つのケースを紹介します。
1.大きい金額の贈与がある場合
一度に多額の贈与をしたい場合、相続時精算課税制度の利用が有効です。
例えば、子どもの自宅購入に2,000万円を援助する場合、通常の暦年課税では多額の贈与税が発生しますが、相続時精算課税制度を活用すれば非課税で贈与が可能になります。最終的には相続財産に加算されますが、当面の資金調達には適した方法です。
2.値上がりが見込まれる財産を保有している場合
贈与時の評価額で相続税が計算されるため、将来値上がりが見込まれる財産がある場合、相続時精算課税制度を利用することで、税負担を軽減できます。
例えば、2,000万円の土地が15年後に7,000万円に値上がっても、相続時には2,000万円の評価額で税額が決まるため、大幅に節税可能。将来的な資産価値の上昇が見込まれるなら、早期の贈与が有益です。
3.収益物件を保有している場合
アパートなどの収益物件を生前に贈与することで贈与税を抑え、将来的な相続税の負担を軽減できます。
不動産を子供に贈与する場合、固定資産税評価額で評価され、贈与額が2,500万円以下であれば贈与税はかかりません。また、家賃などの収益は子供の収入となり、親の所得増加を抑えることが可能。相続時に収益物件が相続財産に組み込まれると、多額の相続税がかかるため、生前贈与は有効な節税策です。
4.基礎控除内で相続する場合
相続財産が基礎控除額内であれば、相続税は発生しません。税負担の心配がないため、相続時精算課税制度を活用するケースが多く見られます。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、この範囲内であれば生前贈与を含めても課税対象にはなりません。財産が少ない場合、子や孫への贈与を円滑に行う手段として利用可能です。
相続時精算課税制度を押さえ最大限節税しよう!

相続時精算課税制度は、子や孫への生前贈与を行う際に役立つ制度です。2,500万円までの贈与税が非課税となり、相続時にまとめて納税します。
ただし、暦年贈与との併用ができないことや、申告期限を守る必要がある点に注意が必要。制度をうまく活用するために、その仕組みをしっかり理解し、適切なタイミングで利用しましょう。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。





