生前贈与とは|メリット・非課税制度・手続き・注意点をわかりやすく解説
2025.07.18

生前贈与とは、生きている間に財産を他者に引き渡すことです。贈与を受けると贈与税がかかりますが、適切に制度を利用することで節税につながります。ただし、注意点もあるため慎重に進めることが大切です。
本記事では、生前贈与のメリット、非課税制度、手続きの流れや注意点をわかりやすく解説します。生前贈与をすべきか迷っている方は参考にしてみてください。
目次
生前贈与とは|相続との違いは?

生前贈与(読み方:せいぜんぞうよ)とは、生きている間に財産を他者に無償で渡すことです。生前贈与を受けた相手は、原則贈与税を納める必要があります。
一方、相続は亡くなった後に財産が引き継がれることです。生前贈与と相続の主な違いは以下を参照してください。
| 財産を渡すタイミング | 税金の種類 | 課税対象者 | |
|---|---|---|---|
| 生前贈与 | 生前 | 贈与税 | 受贈者 |
| 相続 | 死後 | 相続税 | 相続人・受遺者 |
生前贈与のメリット

相続税負担の軽減につながる生前贈与は、贈与時期や相手方を自分の意思で決められるのが特徴です。ここでは、生前贈与のメリットを解説します。
1.相続税負担を軽減できる
生前贈与をしておくと、相続時の財産が減るため、相続税の負担を軽減できます。相続税は、遺産総額が基礎控除額を超えた部分に対して課税されます。つまり、生前贈与によって財産を減らし、基礎控除額以下に抑えられれば、相続税はかかりません。
また、暦年贈与制度を活用すれば、贈与税は非課税のまま相続財産を減らすことも可能です。詳細は後述します。
2.贈与時期や相手方を自分の意思で決められる
生前贈与は、贈与の時期を自由に決められます。相続だと亡くなった後にしか財産を渡せませんが、生前贈与なら受贈者の資金が必要なタイミングで贈与が可能。将来値上がりしそうな株式や不動産は、早めに贈与しておくと相続税負担を減らせます。
また、特定の人に確実に財産を残せることもポイントです。相続だと法定相続人の権利がありますが、生前贈与なら孫や内縁のパートナーなどにも財産を渡せます。
【生前贈与】6つの非課税制度で節税対策を

生前贈与を行う際、非課税制度を活用することで節税対策につながります。ここでは、6つの制度を紹介します。賢く活用して税負担を減らしましょう。
1.暦年課税制度
暦年課税制度とは、毎年110万円までの贈与であれば贈与税がかからない制度です。例えば、1,100万円の財産を110万円以内で継続して贈与すれば、非課税で移転できます。相続財産を減らせるため、相続税の節税効果も期待できます。
ただし、定期贈与とみなされると、課税対象となるので注意が必要です。毎回、贈与契約書を作成して、その都度贈与していることを証明するとよいでしょう。
2.相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の人から、18歳以上の子や孫などに贈与する場合に使える制度で、2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税がかかります。
2024年1月1日からは、この制度に毎年110万円の基礎控除が追加され、より贈与のハードルが下がりました。ただし、この制度を利用して贈与した財産は、相続税の対象となるため注意が必要です。
詳細は、以下の記事を参考にしてください。
3.夫婦間の自宅等の贈与(配偶者控除)
配偶者に居住用の不動産や購入資金を贈与する場合、110万円の基礎控除を加えた最大2,110万円までが非課税になります。制度を適用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- ・婚姻期間20年以上の夫婦であること
- ・同じ夫婦間で初めての利用であること
- ・贈与の翌年3月15日までのその不動産に住み、今後も住み続ける意思があること
4.住宅取得等資金の贈与
2024年1月1日〜2026年12月31日までの間に、両親や祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税となります。住宅の種類に応じた非課枠は、以下のとおりです。
- ・省エネ等住宅:最大1,000万円
- ・その他の一般住宅:最大500万円
対象となる物件の要件の詳細は、国税庁のホームページを確認してください。
5.教育資金の一括贈与
2026年3月31日までに、祖父母などから子や孫へ教育資金を一括贈与する場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税となります。塾や習い事など、教育機関に直接支払う費用以外は、最大500万円までが対象です。
なお、受贈者は30歳未満で、前年所得が1,000万円以下でなければなりません。また、金融機関で教育資金口座を開設する必要があります。
詳細は、国税庁のホームページを確認してください。
6.特定障害者への贈与
特定障害者の生活費や医療費のために贈与する場合、以下のように最大6,000万円まで贈与税が非課税となります。
- ・重度の障害がある人(特別障害者):最大6,000万円
- ・その他の特定障害者:最大3,000万円
制度の適用を受けるには、信託銀行に財産を預け、障害者非課税信託申告書を税務署に提出する必要があります。
【生前贈与】手続きの流れは?

生前贈与は、次の流れで行います。
1.贈与する財産を決める
誰に・何を・どのような目的で贈与するのかを決定する。
2.贈与の課税制度を選択する
暦年課税制度か相続時精算課税制度を選択する。
※併用はできず、相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度への変更はできない。
3.贈与の合意を取る
生前贈与は契約のため、一方的な贈与は認められません。必ず受贈者との合意が必要。
4.贈与契約書を作成する
合意が成立したことの証明として、必ず贈与契約書を作成する。
暦年贈与を行う場合は、定額贈与とみなされないために毎年作成するとよい。
5.財産を受贈者に渡す
受贈者に財産を引き渡す。
生前贈与の注意点5つ
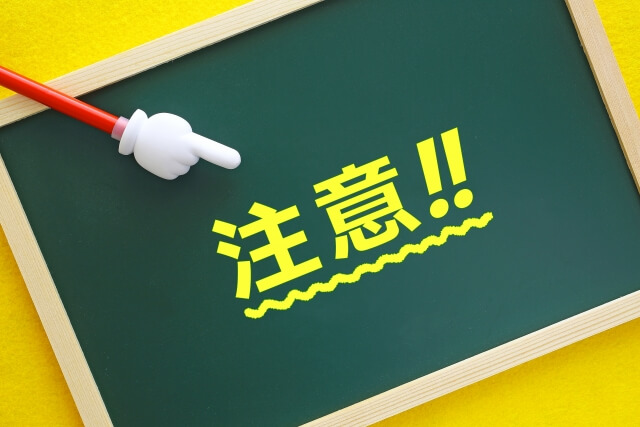
節税メリットのある生前贈与には、抑えておくべき注意点もいくつかあります。ここでは、5つのポイントを押さえておきましょう。
1.名義預金とみなされないようにする
生前贈与として財産を渡しても、名義預金とみなされた場合は相続税の課税対象になります。名義預金とは、実際の管理者と名義人が異なる預金のことです。名義預金と判断されないためには、口座の印鑑や通帳は受贈者自身が管理し、贈与契約書を作成しておくことが大切です。
2.遺留分侵害請求に注意する
生前贈与をする際、遺留分侵害請求に注意しましょう。遺留分とは、法定相続人が最低限もらえる財産の取り分のこと。特定の人に限定して贈与を行うと、不満を持った相続人から遺留分を請求される可能性があるため、事前に話し合っておくことをおすすめします。
3.相続開始前7年以内の贈与は課税される
2024年1月1日以降の贈与からは、「亡くなる前7年以内」に行われた贈与が相続税の課税対象になります。それ以前、2023年12月31日までの贈与は、「亡くなる前3年以内」の贈与が対象でした。
また、毎年110万円の非課税枠を使った贈与であっても、贈与者が亡くなる7年以内の贈与であれば相続税がかかる点には注意が必要です。
つまり、贈与したあとすぐに亡くなると、節税の効果が十分に得られない可能性があります。生前贈与は、できるだけ早めに進めるのがおすすめです。
4.不動産の生前贈与には費用がかかる
不動産を生前贈与する場合、手続きに費用がかかります。例えば、名義変更に必要な登録免許税や、不動産を取得した場合にかかる不動産取得税があります。
手続きや税金の申告を司法書士や税理士に依頼した場合は、それぞれ報酬が発生することに。場合によっては全部で数十万〜数百万円かかるケースもあるため、不動産の贈与は慎重に検討しましょう。
5.定期贈与とみなされると課税対象になる
毎年同じ金額を同時期に贈与していると、定期贈与とみなされて贈与税の課税対象となるため注意しましょう。例えば、1,000万円を10年かけて、毎年100万円ずつ贈与するなどがその例です。
毎年、贈与の時期や金額の変更や、贈与契約書の作成を行うことで、定期贈与と判断されるのを回避できます。
生前贈与の特性を理解し、計画的に準備を進めよう

生前贈与は、非課税制度を賢く活用しながら行うことで、贈与税や相続税の節税効果につながります。
ただし、名義預金や定期贈与とみなされないようにし、遺留分侵害請求のリスクを知っておくなど注意点もあります。生前贈与の特性を理解したうえで、計画的に準備を進めていきましょう。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。






