遺産相続と確定申告|相続税・所得税の申告が必要なケースとは
2025.08.10

親からの相続が発生すると、相続税や所得税の申告・納税が必要になる場合があります。遺産相続した後、確定申告は必要なのか、いくらまで無税なのか気になる方も多いはず。この記事では、相続税と所得税の違い、確定申告が必要となる具体的なケースなどについて詳しく解説します。
目次
相続税と所得税の違い

遺産相続が発生した際に関係する税金には、主に相続税と所得税があります。これらはそれぞれ課税の目的や対象が違うということを知っておきましょう。
相続税
被相続人(亡くなった方)から無償で財産を得た場合に課税されます。一定額以上の遺産を相続すると申告・納付が必要です。
所得税
給与や年金など、個人が働いて得た収入に対して課税されます。そのため遺産を相続しただけでは課税対象にはならず、確定申告は原則不要です。ただし、相続した不動産を売却したり、賃貸などで収益がある場合は、確定申告が必要になるケースもあります。
相続税の申告について

相続税は、遺産総額が基礎控除額を超える場合に課税されます。基礎控除額は、以下の計算式で算出できます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税を申告する必要はありません。基礎控除額を上回った場合でも、適用できる特例があれば課税対象額を減らせるかもしれません。相続税が課税される場合には、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付を済ませましょう。
以下の記事では相続税や基礎控除の計算方法などについて詳しく解説しています。
遺産相続後に確定申告が必要になるケース
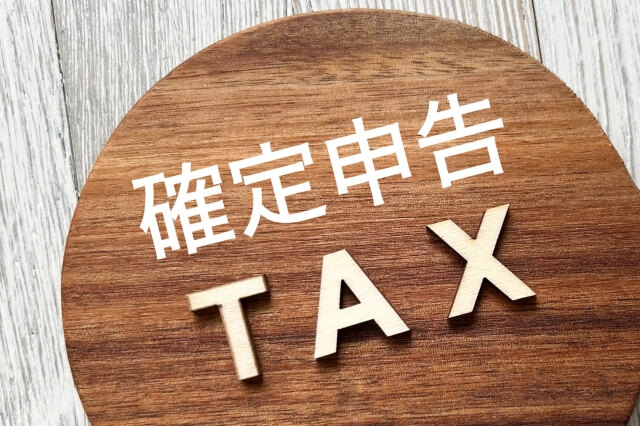
遺産相続では、相続後に確定申告が必要になってくるケースがあります。
ケース1:相続人の確定申告
ケース2:被相続人の確定申告(準確定申告)
ここからは、それぞれのケースについて詳しく解説していきます。
ケース1:相続人の確定申告

基本的に、「相続したことによる確定申告」は必要ありません。しかし、相続した不動産を売却したり、相続したアパートなどから家賃収入を得たりした場合には、相続人は自分の所得税の申告を行うことになります。遺産相続で相続人の確定申告が必要になるケースについてみていきましょう。
1.相続した不動産を売却した
相続した不動産や株式を売却し、譲渡所得が発生すると、所得税の確定申告をしなければなりません。遺産分割するため相続した不動産を売却して遺産分割協議により売却金額を分配する場合は譲渡所得とはなりません。譲渡所得は以下の計算式で求められます。
譲渡所得=売却価格ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額
譲渡所得がプラスの際に所得税が課税されます。なお、特例を適用することで税負担を軽減できる場合もあるので、特例などを調べてみることをおすすめします。
2.相続した不動産から賃料を得た
相続したアパートやマンションなどから家賃収入がある場合、不動産所得として所得税の申告が必要です。相続した不動産は相続税の対象ですが、相続後に発生した家賃収入などは「所得」になるので、確定申告が必要となります。収入から必要経費を差し引いた金額が課税対象です。
3.被相続人の事業を引き継いだ
被相続人の事業を引き継いだ場合も、事業所得として確定申告をしなければいけないケースに該当します。引き継いだ事業から得られる収入や経費を適切に計算し、申告を行いましょう。
4.死亡保険金を受け取った
死亡保険金を受け取った場合、保険料負担者、保険金の受取人の関係によって課税される税金が異なります。被相続人が保険金負担者で、相続人が受取人となっている場合は相続税の対象です。しかし、保険料負担者と受取人が同一の場合、所得税の課税対象となります。
| 被保険者 | 保険料負担者 | 受取人 | 税金 |
|---|---|---|---|
| 被相続人(父親) | 被相続人(父親) | 子ども | 相続税 |
| 被相続人(父親) | 子ども | 子ども | 所得税 |
このように、保険料負担者と受取人によって支払うべき税金が変わってくるので注意しましょう。自分がどちらに該当するのかしっかりチェックしてください。
5.相続した財産を寄付した
相続した財産を国やNPO法人などに寄付した場合、「寄附金控除」の対象となります。そのため、確定申告を行なって所得税の還付を受けましょう。寄付先や寄付内容により控除の適用条件が異なります。事前に確認しておくと良いでしょう。
ケース2:被相続人の確定申告(準確定申告)

準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの間に申告すべき収入があった場合に、被相続人の代わりに相続人が所得税の申告をすることです。ここでは準確定申告が必要になってくるケースについて解説します。
1.給与収入が2000万円以上あった
被相続人が給与所得者だった場合、基本的に年末調整で所得税が精算されるため、確定申告は不要です。しかし、年間の給与収入が2000万円以上の場合、年末調整の対象外なので、この場合には準確定申告の手続きが必要です。
2.複数の事業所から給与収入があった
被相続人が複数の勤務先から給与を受け取っていた場合、準確定申告が必要です。例えばサラリーマンとしての働いて得た給与の他に、副業などをしている場合に該当します。
ただし、副業などの給与が年間20万円以下の場合は申告不要なので、どのくらいの給与があったのかしっかり確認してください。
3.公的年金を400万円以上受給していた
被相続人が公的年金を年間400万円以上受給していた場合にも、準確定申告が必要となってきます。公的年金とは、国民年金・厚生年金などの他に、外国の公的年金も含まれます。対象となる場合は注意しましょう。
4.生前に株式や不動産などの譲渡所得があった
被相続人が生前に株式や不動産などを売却し、譲渡所得が発生していた場合、準確定申告をしてください。譲渡所得の金額や内容に応じて、適切に申告を行いましょう。
5.不動産所得・事業所得などがあった
被相続人が賃貸収入などの不動産所得や、自営業・フリーランスとしての事業所得があった場合、準確定申告が必要なケースが多くなります。これらの所得が年間48万円を超えると、申告義務が生じます。
準確定申告のやり方

準確定申告を行うには、必要書類を揃え、期限内に税務署へ申告・納税をする必要があります。ここからは準確定申告の期限や必要書類について解説します。
準確定申告の期限
準確定申告の申告・納税期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。納付義務者は相続人となり、期限を過ぎると追徴税がかかることもあるので、必ず期限内に申告・納税しましょう。
還付申告に期限はありませんが、5年以内に請求しないと還付を受けられなくなるので注意してください。
準確定申告の必要書類
準確定申告には、通常の確定申告とほぼ同じ書類を準備する必要があります。以下の書類を揃えて申告を行ってください。
【必要書類】
- ・確定申告書
- ・被相続人の源泉徴収票
- ・被相続人の控除証明書
- ・被相続人の医療費の領収書
- ・委任状 など
遺産相続に関わる税金について理解し、申告準備を始めよう

遺産相続に伴う税金には、相続税や所得税があり、状況に応じて申告と納税が必要です。また、被相続人の収入状況によっては準確定申告が求められるケースもあります。
相続に関連する税金の申告には、専門知識が必要なことも多いので、書類集めや確定申告などに不安がある場合は、専門家に相談することを検討してみてください。正しく申告できるように準備を始めましょう。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。






