相続登記の義務化|しないとどうなる?罰則やすぐできないときの対処法を解説
2025.04.05

相続登記が義務化されたことにより、適切に手続きをしなかった場合、罰則をはじめとするいくつかのリスクが生じます。リスクを回避するため、期限内に必ず相続登記を行いましょう。
本記事では、相続登記義務化の内容や手続きをしなかった場合に起こりうること、すぐに対応できない場合の対処法を解説します。
目次
相続登記義務化とは

相続登記とは、不動産を相続した際に名義人を変更する手続きのこと。令和6年4月1日より義務化されました。ここでは、相続登記をおさらいし、義務化の内容を解説します。
【おさらい】相続登記とは?
相続登記とは、不動産を相続した際に、亡くなった人(被相続人)から相続人へ登記名義を移行する手続きのことです。不動産の所有者は法務局が管理する登記簿に記録されており、相続発生時に記録を更新する必要があります。
例えば、亡くなった父親名義の不動産を長男が相続した場合、相続登記によって不動産の名義を父親から長男に変更しなければなりません。
相続登記が義務化された背景
相続登記はこれまで任意の手続きでしたが、令和6年4月1日より義務化されました。相続登記が行われなかったことで、亡くなった人の名義のまま土地が放置され、相続人の特定が困難になったためです。
所有者不明土地が増加し、公共事業の妨げや、環境・治安の悪化といった社会問題を引き起こしました。相続登記義務化は、所有者不明土地の発生を抑制するために導入された制度なのです。
相続登記の対象物件|過去の相続分も?
相続登記の対象となる不動産は、以下のとおりです。
- ・相続で取得した不動産
- ・遺産分割が完了した不動産
- ・被相続人から遺贈された不動産
令和6年3月31日以前に相続した不動産も、相続登記の義務化が適用されます。過去の相続分も対象となるため、早めに手続きしましょう。
相続登記の申請期限はいつ?
相続登記は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。さらに、令和6年4月1日より前に相続した不動産で未登記のものは、令和9年3月31日までに手続きを完了しなければなりません。
相続登記をしないとどうなる?放置する5つのリスク
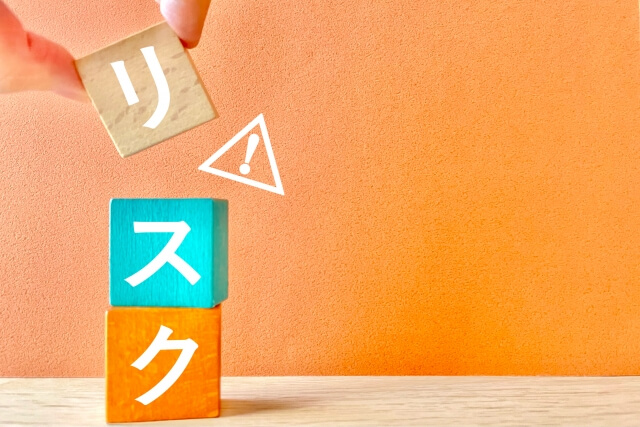
相続登記を放置すると、過料が科される可能性や不動産の売却が困難になるリスクがあります。また、相続人が増えることで権利関係が複雑になるほか、不動産に抵当権等の担保の設定ができません。相続人の一人に対する債権者による差し押さえが起こる可能性もあります。
1.10万円以下の過料が科せられる
相続登記を3年以内に行わなかった場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料が科せられます。
ただし、以下に該当する場合は正当な理由と判断され、過料は発生しません。
- ・相続人が多く、戸籍関係書類の収集や相続人の特定に時間がかかる場合
- ・遺言の有効性や遺産の範囲について相続人間で争いが生じている場合
- ・相続登記を行う人が重病などの健康上の問題を抱えている場合
- ・相続登記を行う人が、生命や心身に危険がおよぶ恐れがあり、やむを得ず避難している場合
- ・相続登記を行う人が経済的に困難な状況にある場合
2.相続した不動産を売却できない
相続登記をしなければ、相続した不動産を売却できないリスクがあります。登記簿上の所有者が故人のままだと、名義人と実際の所有者が一致せず、売買手続きを進められないためです。
また、不動産の名義が曖昧なままでは、相続開始から3年以内の売却で利用できる特例も適用されず、税制優遇が受けられなくなります。
3.相続人が増えて権利関係が複雑化する
相続登記を怠ると、不動産の権利関係が複雑になり、将来の相続手続きが困難になる可能性があります。例えば、父が亡くなり、その相続人である子どもが相続登記をしないまま亡くなると、その子どもや孫も不動産の所有者となり、相続人の人数は増え続けます。
相続人が不明確のまま数代にわたって放置された場合、相続人の特定に時間がかかり、正確な持分がわからなくなるでしょう。結果として、相続手続きの際に相続人全員の合意を得るのは難しくなります。
4.担保として設定できない
相続登記をしないと、相続した不動産に抵当権等の担保を設定できず、融資を受けられません。金融機関は融資をする際に、不動産の登記簿を確認します。
所有者が不明確である場合、不動産を担保として承認してもらえません。相続登記の放置により不動産の価値が下がる可能性もあるため、早めに手続きしましょう。
5.債権者による差し押さえの可能性がある
相続人の中に借金をしている人がいる場合、相続登記をしないと、債権者によって相続した不動産の持分を差し押さえられるリスクがあります。債権者は代位登記を利用して、借金を抱える相続人の法定相続分を相続登記することが可能です。差し押さえられた持分は、その相続人が相続放棄をすれば戻ってきますが(期間制限有)、手続きが複雑になるため早めの登記が無難です。
また、借金をしている相続人が法定相続分に従った相続登記を行い、自身の持分を担保に提供したり売却したりする可能性も。
すぐに相続登記できない場合の対処法|相続人申告登記をしよう

2024年4月から、相続人申告登記の制度が導入されました。相続人申告登記とは、相続開始と相続人の情報を法務局に申し出る手続きのこと。制度を活用することで、遺産分割協議がまとまらない場合や音信不通の相続人がいる場合でも、相続登記義務を履行したとみなされます。
相続人が一人で申し出ることも可能ですが、複数人いる場合は連名での申し出、または各自が個別に申し出る必要があります。あくまで暫定的な手続きのため、遺産分割協議が成立したら3年以内に正式な相続登記を行わなければなりません。
【自分で相続登記は難しい方へ】司法書士に依頼すべきケース

相続登記は自分でも手続きできますが、以下のようなケースでは司法書士に依頼するとスムーズです。
<司法書士に依頼したほうがいいケース>
- ・相続人が複数いる・関係が複雑
- ・仕事が忙しく、平日に時間が取れない
- ・相続した不動産を売却・担保にしたい
- ・相続不動産が複数ある・遠方にある
- ・音信不通の相続人がいる
- ・未成年の相続人がいる
- ・疎遠な相続人がいる
相続登記の司法書士報酬は、5〜15万円が目安。なお、司法書士は相続登記の代行はできるものの、交渉の代理人にはなれません。すでに相続人間でトラブルになっている場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。
一方、以下のようなケースでは自分での手続きも可能です。
- ・法定相続人が一人
- ・平日に時間を確保できる
相続登記義務化|疑問を解消しよう

ここでは、相続登記の義務化に関する質問にお答えします。
1.相続登記を何年も放置したらどうなる?
3年を超えて相続登記を放置した場合は、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
また、権利関係が複雑化し、相続人の把握が困難になるだけでなく、相続した不動産の売却や担保としての活用が困難になります。相続人の中に借金をしている人がいる場合は、代位登記した債権者から差し押さえられるリスクもあるでしょう。
2.相続登記にかかる費用はどのくらい?
相続登記には、以下の費用がかかります。
- ・登録免許税
- ・必要書類の取得費
- ・司法書士報酬(司法書士に依頼する場合)
登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%です。例えば、固定資産評価額2,000万円の不動産を取得した場合、登録免許税は8万円となります。
相続登記には相続人の住民票や戸籍謄本などが必要であり、それぞれ数百円の取得費がかかります。司法書士報酬の費用相場は、前述のとおり5〜15万円です。
【義務化】相続登記をしないとリスクが多い!早めに手続きをしよう

令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことにより、相続を知った日から3年以内の手続きを怠ると、罰則が科されることになっています。それだけでなく、放置により権利関係が複雑になるなど不利益を被る可能性が高くなるため、早めに手続きを済ませることが大切です。
すぐ対応が難しい場合は、相続人申告登記の制度を活用したり、専門家を頼ったりしてリスクを回避しましょう。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。


