土地の相続でやること|分け方や評価方法、相続税の特例・控除も解説
2025.07.18

土地を相続すると、名義変更や相続税の申告などの手続きが必要になります。しかし何からすべきか迷ったり、費用負担を不安に感じたりすることもあるかもしれません。
本記事では、土地を相続した際に行う主な手続きや分け方・評価方法のほか、活用できる特例・控除について解説。不要な土地を手放せる「相続土地国庫帰属制度」も取り上げているので、参考にしてみてくださいね。
目次
土地を相続するときに必要な手続き

土地を相続するにはまず、土地の情報を確認して相続人同士で分け方を決めます。その後名義変更を行い、必要に応じて相続税の申告・納付を行うのが一般的な流れです。ここでは、土地相続に必要な手続きを解説します。
1.土地の情報を確認する
まずは土地の所有者や評価額などの基本情報を正確に把握することが大切です。法務局で取得できる「登記簿謄本」や毎年送付される「固定資産課税明細書」、市区町村窓口で取得できる「固定資産評価証明書」を確認します。
相続する土地が複数ある場合は、すべての不動産情報を漏れなく把握しておきましょう。
2.土地の分け方を確定する
遺言書があればその内容にしたがい、なければ遺産分割協議を行って、誰がどのくらい相続するかを決めます。ただし協議には相続人全員が参加して合意することが必須条件で、一人でも欠けた場合は無効となるため注意が必要。
協議がまとまったら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印で押印します。
3.名義変更手続きをする(相続登記)
遺産分割協議が完了したら、速やかに土地の名義変更(相続登記)を行います。相続登記は2024年4月から義務化されていて、忘れると罰則の対象となる可能性も。
なお、登記申請後、1〜2週間後に法務局から「登記識別情報通知」が発行されます。必ず受け取り、大切に保管しましょう。相続登記の詳しいやり方や必要書類の詳細は、以下の記事を参考にしてください。
4.相続税の申告・納付を行う
相続した遺産のうち、課税対象となる遺産総額が基礎控除額を上回った場合、相続税の申告・納付が必要です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で求められます。
相続税の申告・納付は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならないため、必要に応じて早めに手続きしましょう。相続税について詳しく知りたい方は、以下の記事を参照してください。
相続した土地の分け方

土地はお金のように平等に分けにくいため、相続人同士で話し合いながら状況に合った分け方を選ぶことが大切です。ここでは、相続した土地における4つの分け方を解説します。
現物分割
現物分割とは、長男が土地、次男が預貯金というように、相続人の一人がそのままの状態で特定の遺産を相続することです。シンプルで手続きしやすい方法ですが、公平に分けるのが難しく、土地の価値によっては不公平感が生じる可能性があります。
換価分割
換価分割とは、土地を売却して現金化し、その金額を相続人で分け合うことです。公平に分けやすくトラブルになりにくいですが、売却に手間と時間がかかったり、売却に反対する相続人がいると難航したりする可能性があります。
代償分割
代償分割とは、相続人の一人が土地を相続し、他の相続人に現金で相続分に相当する金額(代償金)を支払う方法です。土地をそのまま相続でき、売却の手間もかかりませんが、相続する相続人には代償金を支払う資力が求められます。
共有分割
共有分割とは、土地を分けずに相続人全員の共有名義にすることです。公平性は保たれますが、処分する際には全員の同意が必要になるなど活用がしにくくなるうえ、将来的に相続人が増えたときに権利関係が複雑化してしまいます。
このように共有分割はトラブルが起こりやすいため、避けるのが無難です。
相続した土地の評価方法

土地の相続税評価額を出す方法は、大きく分けて2つあります。それぞれの特徴を押さえて、適切な方法で算出しましょう。
路線価方式
路線価方式は、市街地や街中のエリアで一般的に使われる方法です。「路線価×土地面積」で計算します。路線価とはその土地が接する道路ごとに決められた価格のことで、国税庁のホームページで確認できます。
ただし土地の形状や間口に応じて補正が必要なため、正確な金額の算出は専門家に依頼するとよいでしょう。
【計算例】
路線価50万円×土地面積100平方メートル=相続税評価額5,000万円
倍率方式
倍率方式は郊外や農村部など、路線価が決まっていないエリアで使われる方法です。「固定資産税評価額×倍率」で計算します。固定資産税評価額は、毎年市町村から送られてくる納税通知書に記載されていて、路線価同様、国税庁のホームページで確認可能です。
【計算例】
固定資産税評価額4,000万円×倍率1.1=相続税評価額4,400万円
相続した土地に適用できる特例・控除
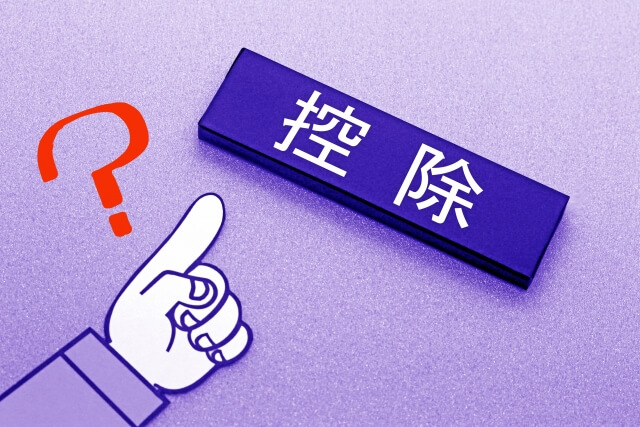
土地を相続したとき、特例や控除を上手に活用することで相続税負担の軽減が可能です。ここでは、2つの特例と6つの控除について解説します。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、土地の評価額を最大80%減額することで、相続税の節税につながる制度のことです。以下のような土地が適用の対象となります。
| 種類 | 概要 | 上限面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用住宅地 | 亡くなった人が住んでいた自宅の土地 | 330平方メートル | 80% |
| 特定事業用宅地 | 個人で営んでいた店舗や事務所の土地 | 400平方メートル | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地 | 経営していた同族会社の事業所がある土地 | 400平方メートル | 80% |
| 貸付事業用宅地 | アパートや駐車場等、貸していた土地 | 200平方メートル | 50% |
複数の土地を相続する場合、特例を併用することも可能です。なお、適用するには条件があるため、専門家に相談することをおすすめします。
農業相続人への納税猶予の特例
農業を引き継ぐ人が農地を相続したとき、相続税の支払いを猶予・免除してもらえる制度があります。
農地は広大なため相続税が高額になりやすく、相続税の支払いのために土地を売却してしまうことも少なくありません。そこで、農業後継者がいなくなることによる農業の衰退を防ぐために同制度が設けられました。
ただし制度を利用できる対象者や条件が細かく設定されているため、税理士などの専門家に相談しながら活用を検討しましょう。
相続税に適用できる6つの控除
控除を適用することも、相続税負担を軽くする方法です。相続税には以下のような控除があります。
| 控除の種類 | 対象となる相続人 | 控除内容 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 全員 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数まで非課税 |
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者 | 1億6,000万円または法定相続分まで非課税 |
| 未成年者控除 | 18歳未満の未成年 | (18歳-年齢)×10万円を税額から控除 |
| 障害者控除 | 18歳未満の未成年 | ・一般障害者:(85歳-年齢)×10万円 ・特別障害者:×20万円 |
| 相次相続控除 | 全員(10年以内に2回相続が発生した場合) | 前回の相続税の一部を今回の相続税から控除可能 |
| 贈与税額控除 | 生前贈与を受けた人 | すでに払った贈与税額を相続税から控除可能 |
相続した土地がいらないとき|相続土地国庫帰属制度とは?

相続した土地の活用予定がなく手放したいときは、相続土地国庫帰属制度を検討するのも一つです。一定条件を満たした場合に国が土地を引き取る制度で、令和5年4月27日から開始されました。相続または遺贈によって土地を取得した人が申請できます。
ただし事前の審査や対象外の土地もあるため、誰でも利用できるわけではありません。詳細は法務省のホームページを確認してみてください。
土地の相続では特例や控除を活用し、負担を減らしながら手続きを進めよう

土地を相続したら、土地の情報を確認して分け方を決め、名義変更や相続税の申告・納付が必要です。相続税の納付が必要かどうかは、土地の相続税評価額を算出することで確認できます。
特例や控除を適切に活用し、税負担の軽減を図りながら手続きを進めるとよいでしょう。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。



