親の死後に家を処分するにはどうしたらいい?方法や費用をまとめて解説
2025.04.22

親の死後はやるべきことが多く、なかでも家の処分をどうしたらよいか迷う方もいるでしょう。親が住んでいた家を放置するとさまざまなリスクがあるため、適切な処分が必要です。
親の死後における家の処分で困らないよう、処分方法やかかる費用、やるべきことや流れのほか、やってはいけないことまで確認しておきましょう。
目次
親の死後に家を処分しない場合のリスクとは?

親の死後に家を処分しない場合、資産価値が低下したり、近隣住民とトラブルになりやすくなったりします。また、犯罪での利用や火災が発生するリスクも。家を所有している以上、固定資産税が発生するうえ、管理を怠った場合は「特定空き家」に指定される可能性もあります。
資産価値が低下する
親の死後に家を放置すると、老朽化が進み、不動産としての資産価値が急速に下がります。放置された家は換気や清掃が行われず、湿気やカビ、シロアリによる腐食が進行しやすくなるでしょう。
その結果、柱や梁が傷み、修繕費用が必要になったり買い手がつかなくなったりする恐れがあります。実家を相続した場合は、なるべく早い段階で処分や活用方法を検討しましょう。
近隣住民とトラブルになりやすい
家を放置すると、近隣住民に迷惑がかかり、トラブルになったりクレームを受けたりする可能性が高まります。放置された家は不法投棄や庭の荒廃による害虫の発生、異臭などの問題を引き起こします。
老朽化した建物が景観の悪化を招いたり、庭木が隣地に侵入したりすることも。家を適切に管理・処分しなければ、近隣住民との関係を悪化させ、トラブルにつながりかねません。
犯罪での利用や火災発生の可能性がある
家を放置した場合、犯罪や火災発生のリスクが高まります。人目がない空き家は犯罪者に狙われやすく、不法侵入や盗難、犯罪拠点として利用されることも。
また、放火をはじめ火災も発生しやすくなります。自然発火や漏電による火災も考えられ、発見がおくれれば建物が全焼する可能性もあります。定期的に訪れたり、適切に処分したりすることで、犯罪や火災リスクを未然に防ぐことが大切です。
固定資産税を払い続けなければならない
親の死後、家に誰も住んでいなかったとしても、固定資産税は払い続けなければなりません。毎年1月1日時点で所有者に課税されるため、放置していれば固定資産税額は積み上がり続けます。
例えば、年間10万円の固定資産税が課される家を5年間放置した場合、税金だけで50万円に達することに。滞納すれば遅延税が課されるリスクもあるため、早めに処分することで税負担の軽減につながります。
特定空き家に指定される
家の管理を怠ると、行政から特定空き家に指定される可能性があります。特定空き家とは、放置すると危険な状態にある空き家のことで、行政が定めた基準を満たすと指定されます。指定を受けると住宅用地特例が適用されなくなり、建物の敷地である土地の固定資産税が最大6倍と大幅に増加。
また、行政の指導や勧告に背いた場合、最終的に行政代執行が行われ、強制的に解体されてしまいます。解体費用等は所有者に請求されるため、金銭的に大きな負担を負うことになりかねません。
親の死後に家を処分する方法4つ

親の死後に家を処分する方法は、不動産仲介業者に依頼する・不動産買取業者に買取を依頼する・相続放棄をする・自治体に寄付をするといった4つの方法があります。各方法について解説していきましょう。
不動産仲介業者に依頼する
親の死後に家を処分する方法として、不動産仲介業者に依頼することが一つの選択肢です。特に築浅で状態がよければ、仲介業者を通じて買い手が見つかりやすいでしょう。
ただし、仲介業者への依頼にはデメリットもあります。買い手が見つかり売却できるまでには、3ヶ月〜半年はかかるのが一般的です。築年数が古く、不便さや修繕が必要な場合は、買い手が見つからないことも。
その場合、建物を解体して土地として売却する手もありますが、高額な解体費用がかかるうえ、建物がなくなることで固定資産税が最大6倍になるリスクが生じます。仲介業者に依頼を検討する場合は、築年数や状態、立地を考慮し業者とよく相談することが大切です。
不動産買取業者に依頼する
専門の不動産買取業者に依頼すれば、老朽化が進んでいたり、立地が悪かったりする家でもそのままの状態で売却が可能です。買取業者は物件を再販・運用目的で購入するため、リフォーム前提で買い取ってくれます。
価格は相場より安くなりますが、すぐに売却できることからスムーズに現金化しやすい点もメリットです。なお、不動産買取業者への依頼メリットは後述しています。
相続放棄をする
親の死後、相続を放棄することで家を手放すことは可能です。相続放棄はプラス・マイナスを問わず全ての財産を放棄する手続きであり、相続発生から3ヶ月以内に行う必要があります。
相続を放棄すると、現金や車など他の遺産も受け取れなくなります。また、固定資産税の支払い義務はなくなりますが、すぐに家の管理責任から逃れられるわけではありません。次に相続する法定相続人が家を管理し始めるまでは、管理責任があります。
相続放棄により実家を手放したい場合は、放棄に伴うデメリットを考慮したうえで専門家と相談しながら進めるとよいでしょう。
自治体に寄付をする
家を処分したい場合、自治体に寄付をする方法もあります。ただし、基本的には受け付けてもらえないことが多いのが実情です。自治体側にとっては、寄付を受け付けることで固定資産税収入がなくなるだけでなく、空き家管理の手間も増えます。
なお、公園や公共施設として利用できるような公益性の高い土地や、自治体が必要としている空き家は受け入れてもらえることも。条件を明確にしたうえで、自治体に問い合わせてみるとよいでしょう。
家の処分を買取業者に依頼する3つのメリット

家の処分を買取業者に依頼すると、時間をかけずに売却でき、遺品処分や掃除の手間が省けるメリットがあります。また、契約不適合責任が免除されることも利点の一つです。
なお、買取を希望している場合は、住栄都市サービスまでぜひご相談ください。
1.時間をかけずに売却できる
家の処分を買取業者に依頼することで、買い手を探す手間が省け、最短数日での売却が可能です。仲介業者に依頼した場合、前述のとおり買い手が見つかるまでに3ヶ月〜半年はかかってしまいます。場合によっては数年かかるケースもあり、すぐに売却し現金化することは困難です。
また、買い手は住宅ローンなどを利用して購入する個人が大半のため、審査に通過できず契約がキャンセルとなるリスクも。一方、買取業者は売り手から直接買い取るため、迅速に対応してもらえます。
2.遺品処分や掃除の手間が省ける
遺品処分や不用品の撤去、掃除の手間が省けることも買取業者に処分を依頼することのメリットです。買取業者は居住用ではなく事業用として、リフォームを前提に物件を買い取るため、残された家具や荷物をそのままの状態で受け入れてくれます。
一方、仲介業者を通じた売却の場合、買い手は一般の個人であるため、他人の荷物が残った状態での売却は困難です。そのため事前に撤去しておかなければならず、撤去費用が発生します。遺品処分や掃除の費用を節約したい場合は、買取業者への売却がおすすめです。
3.契約不適合責任が免除される
買取業者に売却を依頼した場合、契約不適合責任が免除されるケースが多く、引き渡し後のトラブルリスクを軽減できます。契約不適合責任とは、不動産引き渡し後に契約書に記載のない欠陥が発覚した場合、売り手が修繕や損害賠償に応じる責任のこと。
仲介業者を通じて個人に売却した場合、契約不適合責任を負わなければなりません。一方で買取業者は、前述のとおり物件をリフォームして再活用するため、責任が免除されることが多いです。ただし、必ず免除されるわけではないため、契約内容を事前に確認しておきましょう。
【親の死後】家を売却する際にかかる費用

親の死後、家を売却する際にかかる費用として以下が挙げられます。
| タイミング | かかる費用 |
|---|---|
| 家の処分前 | 相続税・相続登記費用・維持管理費用 |
| 家の処分時 | 測量費用・遺品整理/ごみ処分費用・ ハウスクリーニング費用・解体費用・相続放棄費用 |
| 家の処分後 | 仲介手数料・印紙税・譲渡所得税 |
相続税
相続税は、実家を含む遺産相続が基礎控除を超える場合、遺産を受け取った人に課される税金です。被相続人である親が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に申告が必要で、故人の最後の住所地にある税務署に納付します。
原則、現金一括納付のため、10ヶ月以内に実家を売却できなければ、預貯金などで支払う必要があります。納税手続きをスムーズに進めるには、税理士や不動産業者など専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。
相続登記費用
相続した家を売却するには相続登記が必須です。相続登記とは、家の所有権を被相続人から相続人に移す法的手続きのこと。その際、登録免許税や司法書士への報酬などの費用が発生します。具体的な発生費用は以下のとおりです。
- ・登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
- ・司法書士の報酬:相続登記を依頼する際の相場は5〜15万円程度
- ・書類取得費用:戸籍謄本や印鑑証明などに数千円
維持管理費用
相続した家を処分するまでには、ある程度の時間がかかるため、維持管理のための費用が発生します。特に、不動産仲介業者を通じて家を売却する場合は、売却までに時間がかかることから費用負担が多くなる可能性も。
実家が遠方にある場合は空き家管理サービスを利用する選択肢もありますが、月額5,000〜15,000円程度の費用がかかります。維持管理費を抑え、できるだけ早く売却したい場合は、買取を依頼するとよいでしょう。
測量費用
家や土地を売却する際、土地の境界線が不明瞭な場合は測量が必要となることがあります。測量を行うことで土地の面積や形状、隣地との境界線を正確に確定し、近隣トラブルを防げます。特に市街地や地価が高い地域は、測量を求められることがあるでしょう。
測量は土地家屋調査士に依頼し、依頼費用として30〜60万円ほどかかるのが一般的です。なお、隣地が公的機関の所有地の場合は、さらに費用が高くなります。
遺品整理/ごみ処分費用
家を仲介業者に依頼して売却する場合、遺品整理や不用品・ごみの処分が必要です。業者に依頼した場合は費用が発生します。自分で行えば費用はかかりませんが、時間と手間がかかることに。
業者に依頼した場合の費用相場は以下のとおりです。
- ・遺品整理(4LDK以上):20〜60万円
- ・不用品回収(4LDK以上):15〜60万円
処分の手間や費用をかけたくない場合は、不動産買取業者への売却を検討しましょう。
ハウスクリーニング・リフォーム費用
家を仲介業者を通じて売却する際、目立つ汚れがある場合や状態によっては、ハウスクリーニングやリフォームが必要になる可能性があります。建物の状態が悪ければ、購入にはつながらないためです。
ハウスクリーニング費用は、部屋の広さや状態によって5〜15万円程度かかるのが一般的。リフォーム費用は建物や施工場所によって異なりますが、数百万〜数千万円かかります。
なお、不動産買取業者に依頼した場合は、ハウスクリーニングやリフォームは不要であることがほとんどです。
解体費用
家の状態によっては、そのまま売却するよりも解体して更地にしたほうが、買い手が見つかりやすいケースもあります。解体する場合は広さや構造に応じて以下のように費用がかかります。
| 家の構造 | 解体費用 |
|---|---|
| 木造(30坪) | 90〜150万円 |
| 鉄骨造(30坪) | 100〜210万円 |
| 鉄筋コンクリート造(30坪) | 110〜240万円 |
建物の階数にもよりますが、上記以上に費用が発生するケースもあります。空き家の解体費用については、以下の記事も参考にしてください。
仲介手数料
家を不動産仲介業者を通じて売却する場合は、不動産会社に対し仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数料とは、売却価格に応じて発生する手数料のこと。宅地建物取引業法で上限額が定められています。
| 物件の売却価格 | 仲介手数料の計算方法 |
|---|---|
| 200万円未満 | 売却価格(税抜)×5%+消費税 |
| 200〜400万円以下 | 売却価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
| 400万円超え | 売却価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
印紙税
売買契約書を作成する際、印紙税が課せられます。郵便局や法務局、コンビニエンスストアなどで収入印紙を購入し、書面に貼付することで納付。印紙税額は契約金額(売却価格)によって変動し、国税庁により税率が定められています。
なお、2027年3月31日までに作成された契約書は、軽減税率適用の対象です。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
引用:国税庁
譲渡所得税
譲渡所得税は家の売却によって得た利益にかかる税金で、所得税と住民税のことです。売却した翌年の確定申告により納税する必要があります。
税率は家の所有期間によって異なります。相続した実家を売却した場合は、被相続人が実家を取得した日が所有期間の起点です。例えば、親が5年以上所有していた場合、相続してから5年未満だったとしても所有期間は5年超えとみなされ、長期譲渡所得の税率が適用されます。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計税率 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超え | 15.315% | 5% | 20.315% |
【親の死後】家を売却する際に必要な書類
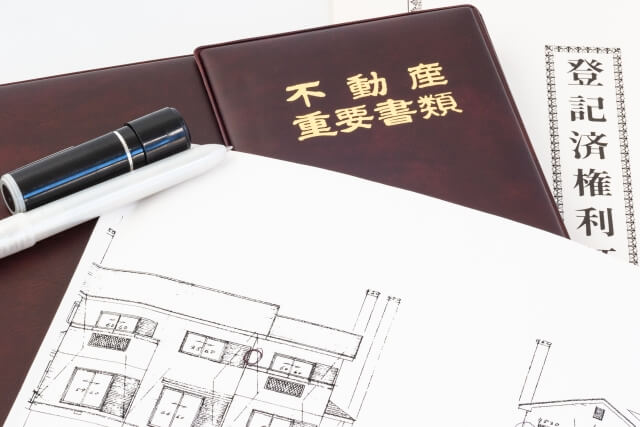
親の死後に家を売却する際、必要な書類は主に以下のとおりです。
- ・本人確認書類
- ・登記簿謄本
- ・登記済権利証(登記識別情報)
- ・固定資産税納税通知書
- ・地積測量図・境界確認書
- ・不動産売買契約書や各領収書
- ・住民票・印鑑登録証明書(登記上の住所と売主の現住所が異なる場合)
- ・遺産分割協議書(相続人が複数人いる場合)
なお、必要書類は状況に応じて異なるため、事前に不動産会社に確認しておきましょう。書類の取得には時間がかかる場合が多いため、早めの準備が大切です。
【親の死後】家を処分するまでにやるべきこと
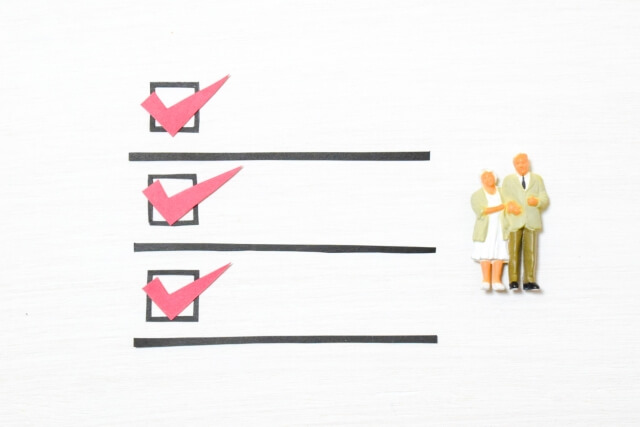
家を処分する前に、親の死後7日以内に死亡届を提出し、遺言書の有無を確認しましょう。そのうえで、相続登記を済ませておく必要があります。
1.死後7日以内に死亡届を提出する
親の死後、亡くなったことを知った日から7日以内に死亡届を提出しましょう。亡くなった親の死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの役所で提出が可能で、夜間や休日でも対応してもらえる場合があります。
提出期限を過ぎると、遺族が5万円以下の罰金を課せられる可能性があるだけでなく、行政手続きで不利になることも。例えば、後述する不動産の相続登記を行う際に被相続人の死亡を住民票で証明できず、手続きが滞る場合があります。
死亡の事実がわかり次第、早めに手続きを済ませることが大切です。
2.遺言書の有無を確認する
亡くなった親が遺言書を残していないか確認することも必要です。遺言書があれば、その内容に従って相続が進むため、遺産相続がスムーズに行われトラブルが起きにくくなります。
一方、遺言書がない場合は相続人全員で遺産相続協議を行う必要があり、合意が難航する可能性も。遺言書が見つからない場合は、実家の金庫や重要書類が保管されている場所のほか、公証役場を確認してみましょう。
遺産分割の方針を決めるため、早めに遺言書の有無を確認し、適切な手続きを進めることが重要です。
3.相続登記をする
不動産を相続後、速やかに相続登記を行いましょう。2024年4月1日より相続登記が義務化され、相続後3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の罰金が科される可能性があります。また、不動産の売却や利用ができなくなるなどの問題も生じます。
相続登記には戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書などの書類が必要です。手続きが複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。必要に応じて専門家に相談しながら、期限内に手続きを済ませましょう。
【売却方法別】家を売却する流れ

家を売却する流れは、仲介業者に依頼する場合と買取業者に依頼する場合で異なります。売却方法別に解説しましょう。
1.仲介業者に依頼し売却する流れ
(1)査定依頼と仲介業者の選定
複数の仲介業者に査定を依頼し、適正価格を比較して自分に合う業者を選定します。複数業者への見積もり依頼は一括査定が便利です。
(2)売却活動を開始
媒介契約を結んだ仲介業者が売却活動を開始し、物件を売り出します。いつ内覧があってもいいように、物件はきれいな状態に保っておくことが大切です。
(3)買主と契約を締結
買い手が見つかったら、売買契約を結びます。物件に瑕疵がある場合は、契約書にその内容を記載し買い手への告知が必要です。
(4)決済と引き渡し
契約に基づいて決済を行い、売却金額を受け取ります。必要書類を準備し、物件の鍵を買主に引き渡して完了です。
2.買取業者に依頼し売却する流れ
家の売却を買取業者に依頼する場合の流れは、以下のとおりです。
(1)買取業者を選定
業者を選定する際は、査定の正確性や過去の実績、顧客からの評価などを判断基準にするとよいでしょう。業者選びに迷う方は、住栄都市サービスまでぜひご相談ください。
不動産会社の選び方については、以下の記事も参考にしてください。
(2)買取価格の交渉
物件の適正価格を理解したうえで、必要書類をもとに不動産会社に交渉します。
(3)契約と決済、物件の引き渡し
不動産会社との契約成立後、売買代金を決済し、物件を引き渡します。決済は銀行振込が一般的です。
親の死後に家の処分でやってはいけないこと6つ

親の死後、活用方法を決めずに家を相続したり、相続したまま放置したりすることは避けましょう。家のむやみな解体や共有名義での相続もおすすめできません。また、相続放棄をしてからの遺品整理は慎重に進める必要があります。
1.活用方法を決めずに相続する
実家の活用方法を決めないまま、無計画に相続することは避けましょう。相続後にそのまま所有し続けると、固定資産税や都市計画税が永続的にかかります。
また、建物の維持管理も欠かせません。活用しないまま所有し続けた場合、管理コストが無駄にかかってしまいます。実家を相続する際は、事前に活用方法や処分方法を決めておきましょう。
2.相続したまま放置する
前述のとおり、実家を相続後に放置するのはやめましょう。管理が不十分になり、特定空き家に指定された結果、固定資産税の負担が増えたり行政代執行が行われたりします。
放置により周辺環境が悪化すると、近隣住民とのトラブルや犯罪リスクにもつながります。売却活動をする予定がなく、放置する可能性がある場合は、最初から相続しない手も一つです。
3.家をむやみに解体する
家のむやみな解体はリスクを伴います。解体すると住宅用地特例が適用されなくなるため、固定資産税が最大6倍に増額。また、新しい建物を再建築する際に、現在の建築基準法に従わなければならないため、制限が生じる可能性があります。
実家を更地にしたまま放置すると、買い手が見つからないまま税金だけを高額に支払い続けることになりかねません。無計画に解体するのではなく、事前に専門家に相談し、計画的な対応が重要です。
4.共有名義で相続する
親の死後、実家を共有名義で相続するのは、リスクがあるためおすすめできません。共有名義とは、2人以上の相続人が同じ不動産の所有者になることです。共有名義にすると相続人全員の同意が必要になり、土地や建物を自由に活用しにくくなってしまいます。
相続人が増えると意思決定が複雑化し、将来的に管理が難しくなる可能性があります。兄弟姉妹で遺産を分割するのが難しい場合は、相続した家を売却して現金化したのち、売却代金を分ける換価分割を検討するとよいでしょう。専門家のアドバイスを受けながら、適切な遺産分割方法を選択してください。
5.相続放棄をしてから遺品整理をする
相続放棄後の遺品整理は不可能ではありませんが、慎重に行う必要があります。相続放棄は、財産に関する一切の権利と義務を放棄する手続きです。遺品整理を行うと、相続放棄の意思表示を撤回したとみなされ、被相続人の財産を受け継ぐことになる可能性があります。
相続放棄後にどうしても家の片付けが必要な場合は、家庭裁判所に遺産管理人の選任を申し立てなければなりません。
なお、相続放棄後であっても、遺品整理をせざるを得ない場合もあります。例えば、被相続人が住宅ローンを抱えており、相続人が連帯保証人になっている場合は、相続放棄をしてもローンの支払い義務は残ります。
また、故人が孤独死した場合は早い段階で遺品整理を行い、特殊清掃の依頼など適切な対応を取らなければなりません。
親の死後、家は適切な方法で処分しよう

親の死後に家を処分しなかった場合、トラブルに巻き込まれたり税負担が増えたりするなどのリスクがあります。そのため、売却や買取依頼などの手段を取り、適切に処分することが大切です。必要な費用や書類、やるべきことを確認し、スムーズに手続きを行いましょう。
なお、不動産買取業者に依頼することで、手間を省きながら短期間で家を売却できます。買取を希望する場合は、住栄都市サービスがご相談を承ります。ぜひ一度ご連絡ください。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。





